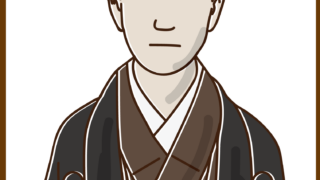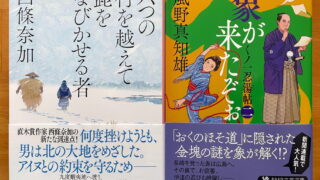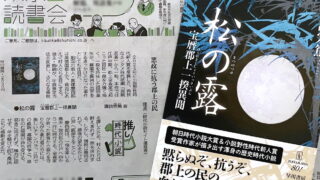蔦屋
蔦屋
(つたや)
谷津矢車
(やつやぐるま)
[芸道]
★★★★☆☆
♪著者の谷津矢車さんは、デビュー作の『洛中洛外画狂伝』で注目される、若手時代小説家。本書の帯には、「“二十代最強の時代小説家”谷津矢車第二作」とキャッチコピーが書かれている。
前作では、安土桃山時代を代表する絵師狩野永徳を主人公に据えたが、今回は江戸の出版プロデューサー、蔦屋重三郎をフィーチャーしている。喜多川歌麿、大田南畝、山東京伝ら、重三郎が手掛けた人気作家たちが続々登場するのも楽しい。
「まあ、しょうがねえよなあ。本屋商売っつうのは所詮運稼業よ」
(『蔦屋』P.4より)
物語は、戯作や錦絵を扱う地本問屋で日本橋に店を構え、本屋業界にこの人ありとまで謳われた本屋、豊仙堂丸屋小兵衛が店仕舞いするところから始まる。何やら、出版不況が続く今の出版業界をも想起させる。
「あなたは地本問屋でしょう。若輩とはいえあたしだってそうなんですよ。同じ地本問屋の気持ちは分かるつもりです。ねえ本当に小兵衛さんは、もう地本の仕事をやりたくなんですか」
反論しようとして口を開いても、言葉が出なかった。
それどころか、口の辺りが震え出してうまく形にならない。
(『蔦屋』P.13より)
一度は本屋稼業に見切りをつけた小兵衛は、蔦屋重三郎の言葉で忘れかけていた夢を思い出す。「一緒にやりませんか。あたしと一緒に、この世間をひっくり返してやりましょうよ」(P.15より)
吉原である。
真っ黒な鉄漿溝を横目に歩き、青い葉を茂らせる見返り柳を見上げながら表門をくぐった先にある極彩色の唐天竺。江戸の男たちの憧憬と、江戸の女たちの憎しみを一身に浴び続ける町。夜になっても煌々と淡い色の光を宿す、眠らずの町。道行く者たちが思い思いに色とりどりの服を纏う、江戸中の色がうるさいほどにぶつかり合う町。『悪所』と呼ばれ、忌まれる町。
(『蔦屋』P.23より)
六七質(むなしち)さんの描く、表紙のイラストレーションは本書のイメージを見事に再現している。
その瞬間、寝惚の目が光った。
重三郎は踊る手を止めた。
「日本橋店の開店祝いだ。あんたに言葉を贈ろう。“吉原に入って名を上げた者は多いが、吉原を出て名を上げた奴ぁいねえ”ってね」
(『蔦屋』P.31より)
吉原に店を構えて細見を売って名を上げ日本橋に店を買った気鋭の本屋・蔦屋重三郎はまさに、“吉原を出て名を上げ”ようとする人間に他ならない。物語は、ここから始まる日本橋での成功譚、辣腕の出版プロデューサーでる重三郎が描かれていく。
「あたしァ、吉原を出る気はありません。が、あたしァ、吉原を江戸の外側にまで広げたい人間でして」
「江戸をまるごと、吉原にするつもりってことかい」
「いや、それとも違いますね。あたしァ、吉原にある鉄漿溝と大門を壊す不埒者になりたいんです。江戸を吉原にしたいのと同時に、吉原を江戸にしたいんです」
(『蔦屋』P.85より)
吉原こそ、重三郎のハートランドであり、彼の出版の秘密が吉原にあることが明らかになっていく。本書のように、吉原と重三郎の関係を喝破した作品はこれまでなかったように思う。第一線の文化人たちが、毎晩吉原でどんちゃん騒ぎを繰り広げることが不思議だったが、読み進めるにしたがってやがて腑に落ちていく。
もうそろそろ付き合いも長くなり始めたというのに、いまだに蔦屋重三郎という男について知っていることは少ない。重三郎という男は、まるで沼のような男だ。その水面を覗き込んでも濁っていて何も見えず、そもそも底なってあるのかさえも分からない。底にとんでもないものを隠していそうでつい覗き込んでしまうが、それでもやっぱりそこが見えることはない。そして、足を踏み入れればそのまままっさかさまに沼に沈まされてしまってもう後戻りはできない。そんな不安を感じさせる。
だからこそ、見てみたい。大人という枷で己を縛っているはずの小兵衛にも抗いがたい、それが他人の秘密というものの持つ魔だ。
(『蔦屋』P.118より)
本書の面白さの一つとして、かつて地本問屋の主人で、今は使用人として重三郎の店を切り盛りする、堅物で仕事人間の丸屋小兵衛が語り手を務めて、重三郎の型破りな部分を浮き彫りにするところ。
商人は臆病でなければやっていけない。損を小さくするためには大勝負を仕掛けずに小さくこまごまと動くしかない。しかし、この重三郎という男は、元手さえ稼いでしまえばあとは躊躇がない。まるで賭場でふんどしまで賭けてしまうかのように金を集中させる。
山師、ともいえる。
(『蔦屋』P.198より)
「世の中には色んな人がいます。時代の流れに器用に乗れる人もいます。でもその反面、自分の生き方を自分では変えられない人もいます。そもそも生れついた瞬間から、狭隘な生き方しかできない人たちもいます。偏狭な枠組みの中でしか生きられない人っていうのはたくさんいる。それを、あたしァ吉原で知りました。だから、あたしァ決めたんです。そういう人たちの側に立つ、って」
(『蔦屋』P.232より)
そして、物語で重要な役割を演じる、朋誠堂喜三次と恋川春町の二人の戯作者も、武士でありながら、その枠内だけでは生きられない、ある意味で偏狭な側にいる人たちといえる。
特に宣伝は打たなかったらしい。というより、宣伝を打つ余力などなかったのだろう。とにかく、何の前触れもなく売り出したその役者絵は、まず吉原で話題になり、それが日本橋での売り上げにつながった。他の版元は『なぜ何の宣伝もしていない絵が売れるのだ』と目を回しているだろうが、これが蔦屋重三郎のやり方だ。重三郎は吉原に身を溶かして様々なところにこの絵師、写楽のことを紹介していたのだろう。吉原という地が、江戸の出版ひいては文化のへそであることを知っているのは、ただ耕書堂だけだ。張り巡らされた地下水脈を使い、そこに少しずつ毒を流し込むようにして写楽を解き放った。その結果がこの大評判だ。
(『蔦屋』P.306より)
田沼時代の天明から、嵐のような寛政の改革、そしてその後を、蔦屋重三郎と仲間たちとともに活写した傑作時代小説である。次回作もますます楽しみになった。
主な登場人物◆
蔦屋重三郎:吉原の本屋「耕書堂」
丸屋小兵衛:日本橋の地本問屋豊仙堂の主人
寝惚:重三郎の遊び仲間
六樹:重三郎の遊び仲間
勇助:絵師。後の喜多川歌麿
大田南畝:狂歌師、戯作者
朋誠堂喜三次:戯作者で、某藩の江戸留守居役
宿屋飯盛:狂歌師で、公事宿の店主
お春:重三郎の妻
吉蔵:重三郎の子
伝蔵:煙草屋。山東京伝の名で戯作をする
恋川春町:戯作者で、酒上不埒の名で狂歌も詠む
銀蝶:吉原の女郎
お雅:吉原の遣り手
物語●
日本橋の地本問屋豊仙堂丸屋の主人小兵衛は、家業を傾け、店を売りに出して隠居生活に入ることを決意した。その小兵衛の前に、小兵衛ごと店を買うという若造が現れた。吉原の小さな本屋の主人・蔦屋重三郎だった。
小兵衛は、「一緒に世間をひっくり返してやろうじゃないか」と重三郎に声をかけられて、地本に夢をかけた若い日の気持ちを思い出す。
ところが、重三郎は、日本橋の店を再開させる様子がなく、連日のように小兵衛を吉原に連れてきて、寝惚や六樹と呼ばれる連中と酒を飲んで遊んでいるばかりだった……。
目次■なし
カバーイラストレーション:六七質
装幀・本文デザイン:野村勝善(HANA*Co)
時代:天明三年(1783)
場所:日本橋通油町、吉原、小伝馬町、深川、ほか
(学研パブリッシング・1,300円+税・2014/04/08第1刷・364P)
入手日:2014/03/22
読破日:2014/04/21
■Amazon.co.jp
『蔦屋』(谷津矢車・学研パブリッシング)