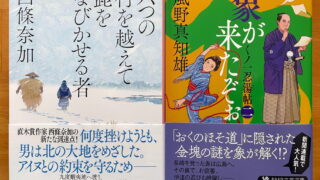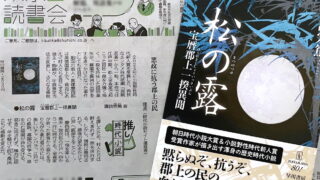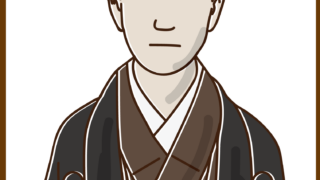(らくちゅうらくがいがきょうでん・かのうえいとく)
(やつやぐるま)
[芸道]
★★★★☆☆
♪禁裏から許しを得て、町衆向けの扇絵制作の特権を持つ狩野家に生まれた源四郎。小さい頃から絵筆をとりながらも、狩野派の伝統や常識にとらわれまいと足掻く若者の苦悩と成長を描く、戦国時代を舞台にした芸道小説。
作者の谷津矢車さんは、1986年生まれで、第18回歴史群像大賞優秀賞を受賞。本作が小説デビュー作(デビュー時、なんと26歳!)。
安部龍太郎さんの『等伯』や萩耿介さんの『松林図屏風』など、同時代の絵師長谷川等伯を描いた作品が注目されるなかで、第一人者の狩野永徳を題材として取り上げたところがケレン味がなくて素晴らしい。
「今回献上させていただく絵が、極めて奇妙な成り行きで生まれ、今ここに存在することをご理解いただければ、というだけのことにございますよ。この絵の様は、尾張の田舎領主であったお方が、気付けばこうして天下に号令している様とも似ていましょうや」
不遜。そして、信長は心中に熱い炎が燃えたぎり始めているのを自覚していた。怒りではない。この若い絵師は何を考え、どんな手を打ってくるのだろう、という深い疑問。この絵師は、天下の号令者である織田信長に、何かを挑もうとしている。
ならば、受けて立つのがわしであるか――。信長は肚を決めた。
(『洛中洛外画狂伝 狩野永徳』P.13より)
冒頭で、狩野源四郎(若き日の永徳)は、織田信長に引見して、絵を献上しようとする。緊張感みなぎる天才絵師と若き天下を狙う男の対峙シーン。
「師匠は、絵を描くとき、心が躍ることはありませぬか」
「心が、躍る?」
「ええ。真っ白な紙の上に筆を下ろす時。その一瞬、世の中の陰陽が交わるような感覚にいつも襲われます。そして、この紙の上に何を描いてやろうか、と愉快な思いになることはありませぬか」
ふん。松栄は何も答えず、鼻を鳴らして立ち上がった。そして、くるりと踵を返してしまった。が、思い出したことがあったかのように振り返り、ぼそりと答えた。
「もしかしたら、昔はそんな思いもあったかもしれぬ。が、今はもうない。そして、その思いは魔境であることを、わしは知っておる」
(『洛中洛外画狂伝 狩野永徳』P.56より)
源四郎は幼い頃から、狩野派のバイブルである粉本(手本)で絵を描くことを嫌い抜いていた。そのため、師匠でもある父の松栄と絶えず争いが絶えなかった。
源四郎は、貴人から屋敷へ呼ばれて、真っ白な紙が貼られた扇に、「日輪」の絵を描けと命じられる。そして、粉本を用いずに、実際に日輪のもとで描くことを試みるが…。
今ならば、見える。源四郎は空を見上げた。天の上には、いつもならば全天の支配者としてその本性を見せぬ日輪が、人間の目に捉えられる姿として、そこにあった。
嘆息した源四郎は誰かに急き立てられるようにして筆を振るい、紙の上に天地の光景を写し取っていた。
この瞬間、源四郎は確かに捉えていた。絵を描くということの、手触りを。そして、何かを描くということの内奥に控える魔の横顔を。
(『洛中洛外画狂伝 狩野永徳』P.73より)
貴人は、時の将軍足利義藤(後の義輝)であった。
「源四郎、錆びついた魂を動かしてみよ」
「錆びついた、魂?」
「世間の荒波、と言うであろう? 世間は塩水なのだよ。だから、世間の荒波に揉まれているうちに心が錆びついてしまう。特に、わしやお前のような細工品の場合はの。だが、世間が塩辛いのをどうすることも出来ぬし、それをあげつらっても何が変わるわけでもない。要は」
元信はいつしか、源四郎にきっと向いていた。
「錆びついても動く、そういう魂が大事なのかもしれぬな」
錆びついても動く魂。(『洛中洛外画狂伝 狩野永徳』P.150より)
人生に迷ったときに、言ってほしい名言だな。
常識にとらわれない天才ゆえに、父と対立しながらも狩野家の伝統を乗り越えようと苦悩する源四郎を温かく見守るのが、粉本をつくり狩野派の土台を築いた祖父の狩野元信。
「わしは、狩野の絵の先を見る」
「ぐっ……!」
打つ手がないことを悟ったのか、松栄はその場から消えた。
一人残された源四郎は、また絵に向かい、しばらくしてやってくる天と地の気配に耳を澄ました。
(『洛中洛外画狂伝 狩野永徳』P.227より)
ずっと源四郎の脳裏にあった光景である。自分を通す。すると周りに人がいなくなっていく。そうして最後には、暗い獣道を自分一人で歩く羽目になってしまう。しかし、一方で源四郎には見えている。暗く狭い獣道の涯に一条の光が差し込んでいるのが。
要は、どちらを取るか。
(『洛中洛外画狂伝 狩野永徳』P.227より)
この作品は、狩野源四郎と、足利義輝、松永弾正、織田信長ら京の町を統治し、天下に号令しようとする権力者たちとのやり取りを通して、戦国時代を鮮やかに描き出している。そしてそこには、京の町に暮らす人びとの姿も源四郎の目に映ったままに織り込まれている。まるで、源四郎の手による名画「洛中洛外図屏風」のように。
本書は、「洛中洛外図屏風」の制作秘話であり、それは戦国時代に天下を狙う男たちの闘いの物語でもある。
気が利いていることに、この本の見返し(表紙と本文をつなぐ紙)に、「洛中洛外図屏風」の画像が使われていて、源四郎が描いた絵の凄さが伝わってくる。
●上杉博物館 「洛中洛外図屏風」
http://www.denkoku-no-mori.yonezawa.yamagata.jp/rakuchyu_rakugai.htm
信長の前でキリスト教宣教師との宗論に敗れる朝山日乗を想起させる、怪僧日乗が登場するのも面白いところ。
主な登場人物◆
狩野源四郎:狩野家若惣領で、後の狩野永徳
狩野松栄:源四郎の父で、狩野家惣領
狩野越前元信:源四郎の祖父で、松栄の父。狩野家総元締
狩野元秀:源四郎の弟
廉:土佐家の縁者の娘
福助:膠小屋の老人
平次:福助の孫
安:扇商の美玉屋の若主人
日乗:陰陽師で僧
足利義藤:室町幕府十三代将軍で、後の義輝
松永弾正:三好長慶の家臣で、京の差配を任されている
宗養:連歌師
近衛前嗣:関白左大臣で、後の前久
織田信長:尾張の領主
物語●
天文十七年、狩野源四郎は六歳のとき、実物の蝶を捕まえて描いた絵のことで、父で師匠の松栄から手厳しく叱られた。参考にするのは粉本であり、実物を見て描くことは魔境に入ることであると、繰り返し小言をもらった。
父との言い争いにより絵を描くことに倦んだ源四郎を祖父の元信が京の町に連れ出した。辻の端っこで、賭け闘鶏をしているのに出くわして、はぐれ狼のような武者を思い起こさせる二羽の鶏の姿に興味をもつ。墨の持ち合わせのない源四郎は、鼻血を墨の代わりにして懐紙に、夢中で絵を描きはじめた。
そのとき、十人あまりの侍を従えて貴人の少年が闘鶏の見物にやってきた。闘鶏の勝負がつくと、少年は源四郎の鼻血に気付き話しかける。そして、懐紙の上に血で描かれた鶏の姿を、「見事な絵ぞ」と褒めた…。
目次■プロローグ/1 軍鶏/2 錆色/3 魔境/4 競絵/5 業火/エピローグ