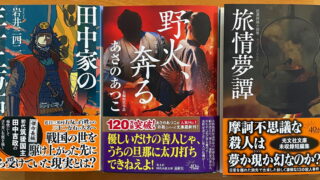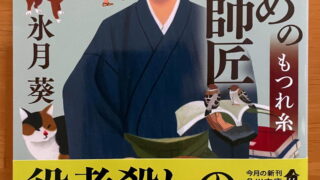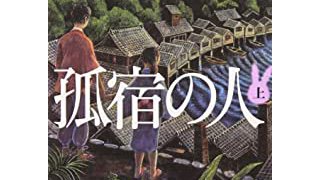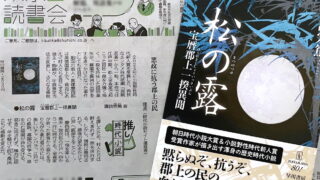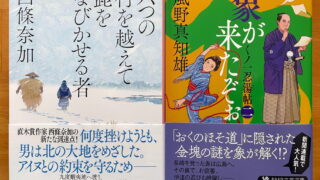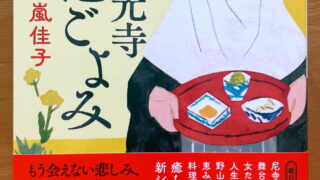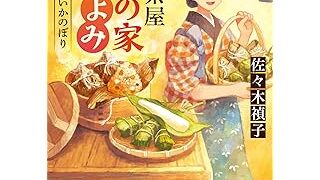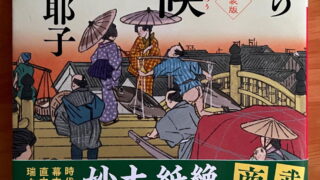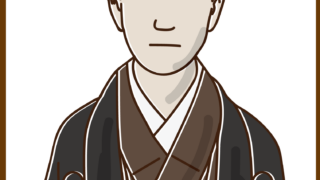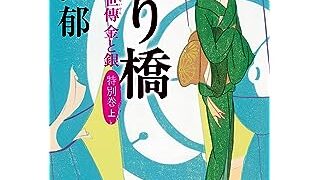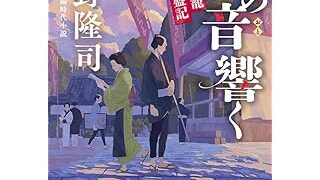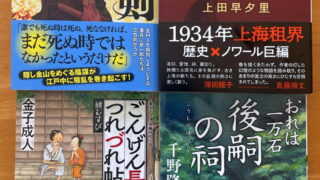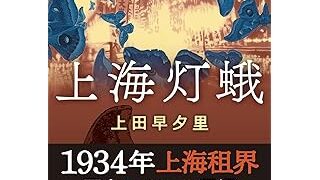(かえりざきさんざ・おはなばたけやくひちょう)
(やまだたけし)
[武家]
★★★★☆
♪著者の山田剛さんは、2010年「刺客―用心棒日和―」で第17回歴史群像大賞佳作を受賞し、改題した『大江戸旅の用心棒 雪見の刺客』でデビュー。著書には、『大江戸旅の用心棒 露草の契り』『中町奉行所内与力 かみそり右近』がある。本書は文庫書き下ろし。初老の藩士・峠三左衛門(三左)の活躍を描くエンターテインメント武家小説。
三左は、譜代笛木桜井家二万三千石の御花畑役を務めていたが、三年前に隠居して家督を息子に譲り、千日を越す退屈な日々を送っていた。
笛木藩は架空の藩だが、三河の海に面した小さな藩ながら、南北に広がる肥沃な土地と豊かな森林資源、加えて温暖な気候にも恵まれて、藩の財政も裕福という設定。
三左が務める御花畑役とは、普段は城内や藩主の邸宅の庭の管理をするのが主な役目。藩の命令で遠国御用、すなわち、隠密の任務も担っていた。
時代は、家継が七代将軍に就いたころ。注目したいのは、木挽町に山村座(絵島生島事件は正徳四年の出来事)が描かれていて、中町奉行所も登場する。
昨年は雨、それも豪雨が多く、日本各地に天災が起きた。この笛木も例外ではなく、地滑りが発生し、山の麓の集落が泥流に呑み込まれ、多くの命が奪われたのである。過度の伐採が地滑りをひき起こした原因の一つではないかと囁かれた。
笛木の集積場には、今も、出荷停止となった木材が山と積まれ放置されたままになっていた。(『返り咲き三左 御花畑役秘帖』P.21より)
この当時は植林という概念と技術がなく、ある程度木を伐り出すと〈留山〉と言って、入山を禁止し、自然に木が育つの待つしかなかったという。さて、物語では、幕命で出荷停止となったこの木材が事件をもたらすことに。
若侍は気恥ずかしげに逸らした目を三左衛門の脇差に落とした。
「珍しい刀だな、拵えも変わっている」
再び目を上げて、三左衛門を見た。
「所持している者は、そうおるまい」
「海部刀でござる」
海部拵といって、桜皮や樺皮を細工して鞘や柄に巻いてある。
「阿波か」
「阿波の刀だと知っている者も、そうおるまいと存ずる」(『返り咲き三左 御花畑役秘帖』P.34より)
三左衛門の脇差は、海部刀(かいふとう)と呼ばれる、刀身の峰の部分が鋸刃になっているのが特徴。恥ずかしながら、こんな刀があることをこの本で初めて知った。
どっと、男たちの野太い歓声が聞こえた。
「火消人足どもが、酒でも酌み交わしているのであろう」
玉砂利の中庭を挟んだ向かいに火消人足の長屋がある。
官兵衛の役職は、国許では手廻組だったが、今は火消預方である。火消預方は通称、火消方と呼ばれ、笛木桜木家江戸屋敷の各自火消を束ねる御役目だった。(『返り咲き三左 御花畑役秘帖』P.61より)
江戸詰で同い年で永年の朋輩の官兵衛は、三左の江戸再出仕と再会を祝い、藩邸内の長屋で馳走でもてなした。その最中に、半鐘が鳴り、官兵衛は火消人足を率いて出動することに…。
この作品では、物語の中で適切に江戸に関する解説が加えられている。各自火消とは、諸大名が家ごとに組織した火消をいい、自身の屋敷を火災から守るために、火消し人足を常雇いしていた。
三左衛門は顔を伏せたまま、おろおろと城太郎に向き直った。
「若、若の仰せの通り、三左衛門は泣き虫でございました。この泣き虫奴を、どうか独りに、独りにしてくだされ……」(『返り咲き三左 御花畑役秘帖』P.128より)
(自分もそうだが)年を取ると、男は涙もろくなってしまうのかもしれない。英雄然としない、等身大の主人公がほほえましい。
「鷹の巣は藤と橘何れに在りや、御側に三つ、峰に二つ、他は一つ」
三左衛門は、声に出して読み上げた。
「何じゃ、それは」
庄兵衛も紙を覗き込んで小首を傾げた。
その間に、城太郎がもう一枚書き上げた。
同じように三左が読み上げた。
「終わりなき夜に澄む月影あかければ、いざ漕ぎ出でぬこの宝船」(『返り咲き三左 御花畑役秘帖』P.223より)
物語の中で事件を読み解く鍵として、判じ物と歌の二つが提示される。うーん、すぐに解けないが面白い。
「御花畑役とは、隠密か」
「花を育て、山の恵みを管理し、笛木に災いが及ばぬよう、常に先々に心を配り、力を尽くす御役目にございます」(『返り咲き三左 御花畑役秘帖』P.285より)
終盤で藩外のある人物から、御花畑役について尋ねられた三左の答え。この物語の読み味がよいのは、主人公が、名もなき花を慈しむように命を慈しみ、黒衣(くろご)のように人知れず御役に立つことを願って行動しているからかもしれない。
文庫書き下ろし時代小説で、自分に合った作品、作家と出会うことは重要である。山田さんの作品をもっと読んでみたいと思った。
主な登場人物◆
峠三左衛門:隠居で笛木藩の元御花畑役
初枝:三左衛門の妻
由枝:三左衛門の母
佐保:三左衛門の倅の嫁
海老原庄兵衛:隠居で笛木藩の元納戸役
木村官兵衛:三左衛門の長年の朋輩、笛木藩の火消預方
梶山貫太郎:笛木藩城代家老
間部越前守詮房:将軍家側用人で、高崎五万石の大名
桜井日向守直実:笛木藩藩主
お美和:日向守の正室
城太郎:日向守の次男
多々良重右衛門:御留守居役
三雲文平:笛木藩江戸詰藩士
佐吉:染井村の若い植木職人
尾張屋藤右衛門:尾張家ご贔屓の菓子司の主、花好きの隠居
村松休之助:御召馬預役
一枝数馬:馬乗役
三崎:中町奉行所同心
三木伊賀守信孝:黒北藩藩主
志村正二郎:黒北藩藩士
日野屋欣兵衛:黒北藩御用達の材木問屋
南原宏一郎:御用坊主
徳川権中納言吉通:尾張徳川家当主
浅草の留守居茶屋〈菊膳〉の女将
物語●
尾張藩の東に隣接する小藩笛木藩の元御花畑役・峠三左衛門(通称三左)は隠居して、無聊を囲む日々を送っていたが、ある日、江戸藩邸への再出仕の命が下る。御花畑役の欠員補充だといういうが、三左は御花畑役のもう一つの役目である隠密御用だと秘かに期待していた。幕命で伐り出した御用木材の突然の出荷中止に、側用人間部詮房の仕業との噂があったからだ。
だが、江戸で三左を迎えたのは意外な人物で、笛木藩の若君桜木城太郎の悪い噂も聞かされる。そんな折に、笛木藩を危難が襲い、周到に仕掛けられた罠の匂いを嗅ぎ取る三左の周りにも事件が…。
目次■第一章 江戸へ/第二章 葵の風/第三章 国替え/第四章 襲撃/第五章 逆転
カバーデザイン:齋藤視倭子
時代:正徳三年(1713)三月
場所:笛木(尾張藩の東隣りにある架空の藩)、高輪の大木戸、木挽町山村座、巣鴨、染井村、小石川五軒町、清水橋御門外、音羽、向島、小石川茗荷谷、新吉原、江戸城大手門前、浅草、深川猿江町、芝六軒町、四谷尾張藩中屋敷、ほか
(学研パブリッシング・学研M文庫・638円・2013/04/23第1刷・307P)
入手日:2013/04/18
読破日:2013/04/26