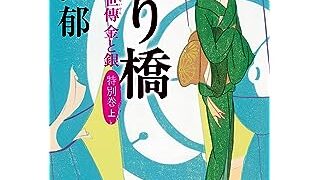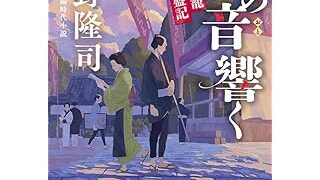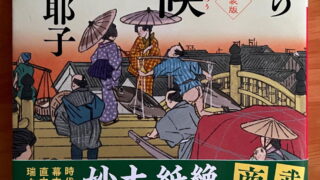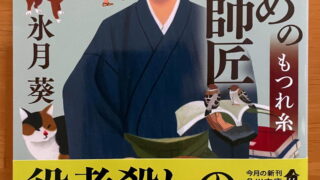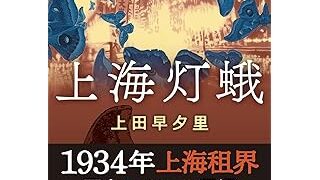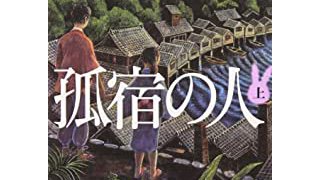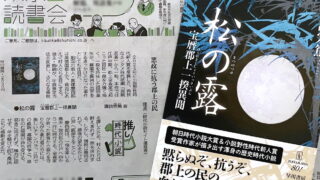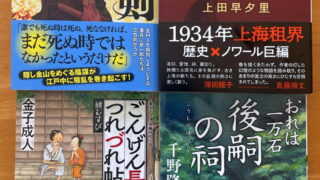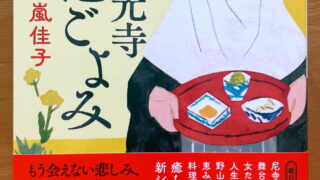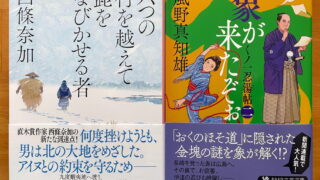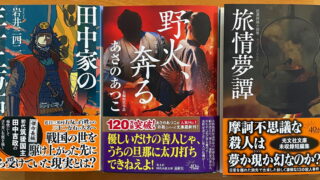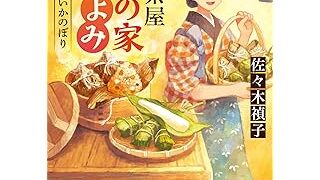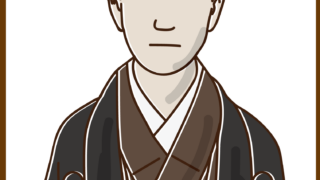(えどまちぶぎょうしょぎんみひかえ はんしょう)
(うえまつみどり)
[捕物]
★★★★☆
♪気鋭の時代小説家植松三十里さんの文庫書き下ろしシリーズ。第一弾は、「八百屋お七」を取り上げている。「八百屋お七」というと、火事で避難先の寺の寺小姓と恋仲になり、その寺小姓に逢いたくて放火をしたということぐらいで、実はよく知らない。
八百屋お七がなぜ火をつけたのか? その謎解きの鍵となる、若い女性の心理がしっかり描かれていて面白かった。
では、時代考証をしっかり押さえようという著者の姿勢がうかがえて好感が持てる。たとえば、お七の着ている寛文模様の小袖。右肩に目立つ柄が入り、裾に向かって絵柄が続くデザイン。お七は、町の八百屋ではなく、スーパーのような大店のお嬢様であり、流行を着ている。
主人公の永田誠太郎は、南町奉行所の定町廻同心だが、時代設定が天和二年(1682)ということで、その所在地が数寄屋橋御門内ではなく、呉服橋御門内に置かれていたことも押さえられている。ちなみに、宝永四年(1707)に数寄屋橋御門内に移転している。
あとがきで、植松さんは、十七歳の娘がなぜ死罪となるとわかっている放火に奔ったのか、本当に男に会いたかっただけなのだろうか。また、十五歳と言うことも可能で、そうすれば減刑されたのに、それを拒んだのか? 現代の少年犯罪に通じる、物語の執筆動機を明かしている。
このシリーズは、江戸時代の謎だらけの事件を、八百屋お七の時代に限らず、時空を超えて、物語展開していくという。『半鐘』の次の「江戸町奉行所吟味控」は、10月の発行予定ということで待ち遠しい。
物語●駒込の大圓寺を火元とする火事が起こり、南町奉行所定町廻同心、永田誠太郎は、野次馬の中に不審者がいないか、観察を続けた。怪しい人物はいなかったが、人垣の中に、寛文模様の小袖を着ている十六、七歳の娘が目に留まった。近くの本郷森川町の大きな八百屋の娘で、お七だった。大圓寺の火事は小坊主の不手際からの出火だったが、その二月後に、お七が火付(放火未遂)で捕まえられた。奉行の甲斐庄飛騨守正親は、何か事情があるのではないかと、誠太郎に探索を命じた…。
目次■第一章 師走の黒煙/第二章 桃の節句の吟味/代参章 振袖火事/第四章 女掏摸/第五章 寺男との出会い/第六章 お七の生い立ち/第七章 秘められた事件/第八章 泪橋/あとがき