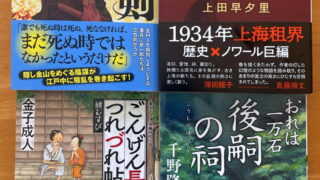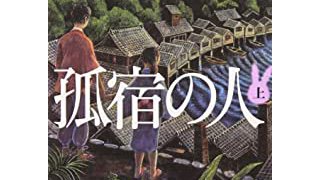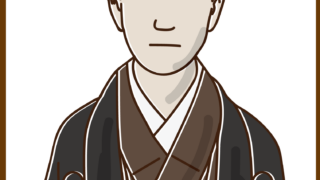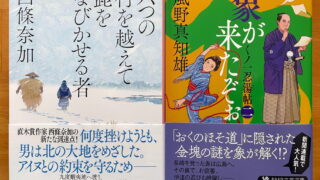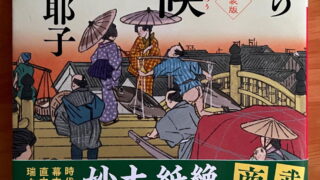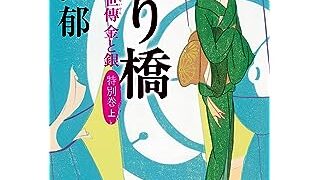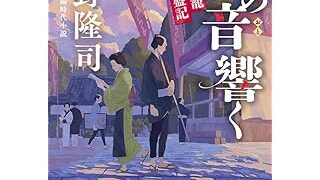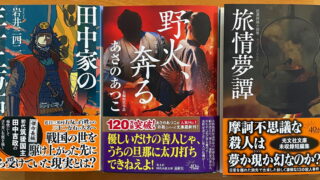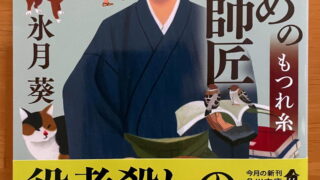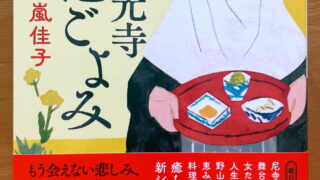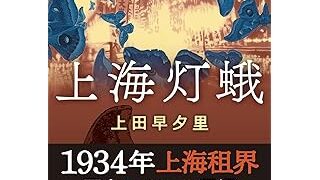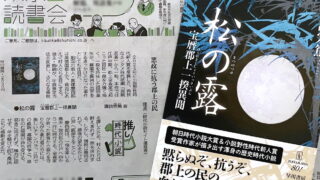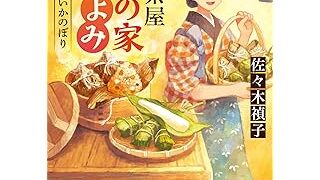秘剣埋火
(ひけんうつみび)
戸部新十郎
(とべしんじゅうろう)
[剣豪]
★★★★☆
♪無外流(開祖は辻月丹、『剣客商売』ですっかり有名になった)の術者でもある、戸部さんの大好評の「秘剣」シリーズ。剣の秘技と剣客にともなうエピソードを綴りながら、剣の神髄を明らかにしていくスタイルが何とも面白い。
今回は、作者の出身地である、加賀で隆盛した中条流がらみの話が3篇、『吉原御免状』(隆慶一郎著・新潮文庫)でおなじみの庄司甚右衛門が登場する(甲州の盗賊・鳶沢甚内こと、高坂甚内も登場)話が2篇収めてあるのが特徴。名は潜、字は子竜。兵原と号し、その居住するところを“平原草蘆”と名付け、近藤重蔵、間宮林蔵に合わせて“蝦夷三蔵”とも呼ばれた奇傑、平山行蔵が登場する「餓鷹」と、名もない(架空の)呂九平の遣う剣の妙技が面白い「松葉」も印象深い話だ。
物語●「吹毛」御子神典膳は、又助を連れて江戸にやってきた。そこで、仕官の話で小幡勘兵衛の屋敷を訪ねた…。「必勝」必勝は新陰流“九箇(くか)ノ太刀”の第一にあげられている。柳生石舟斎の四男・五郎右衛門はこの“必勝”を得意としていた…。「微塵」黒田長政にとって、信太角左衛門はたいそう印象の薄い家来だった。角左衛門は笛の名手でもあった…。「埋火」越前六十八万石・松平秀康の“御弓ノ者”に阿波賀小四郎という者がいた。中条流の遣い手でもあった…。「南蛮」加賀金沢城下の南蛮寺にいる、前田家の客臣・高山南坊(みなみのぼう)のもとに、中条流で“名人越後”と呼ばれていた富田(とだ)越後守重政が訪ねてきた…。「雙六」中条流に雙六(すごろく)という秘術があった。越前の太守・松平忠直の側小姓にあがった山崎弥五郎は、この太刀を心得ていた…。「柳雪」霞ヶ関の柳生屋敷へ日本橋の吉原廓の宰領人、庄司甚右衛門がやってきた。甚右衛門は、かつて風魔小太郎を頭領とする相州乱破の一味であった…。「参差」葭原のおやじ、庄司甚右衛門は、最近、若衆髷の匂うような美しい少年・藤若を連れ歩いていた…。「餓鷹」四谷伊賀町に、文武ニ道に卓越した老伊賀組同心が住み、毎朝決まって四つ(午前四時)から、武芸の稽古を始めていた。この老同心、名前を“平山行蔵”といった…。「松葉」金沢藩士・堀万之助の従者・呂九平は、主人を襲おうとした蓑を着けた浪人者を、得意の“松葉”で退けた…。
目次■吹毛|必勝|微塵|埋火|南蛮|雙六|柳雪|参差|餓鷹|松葉|解説 前島不二雄