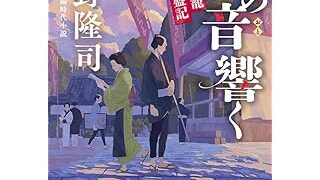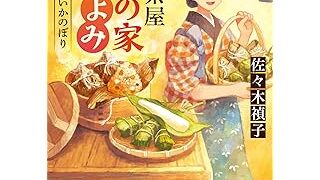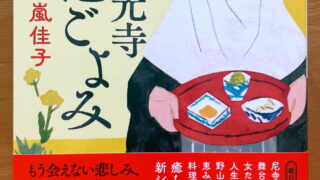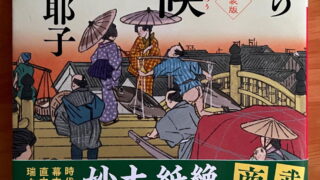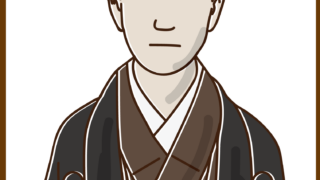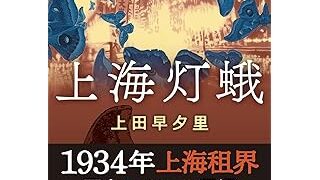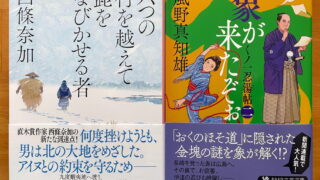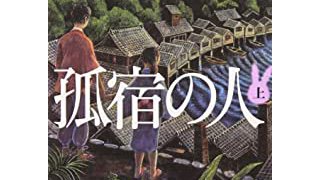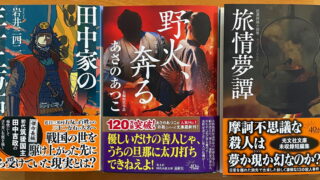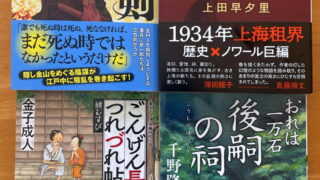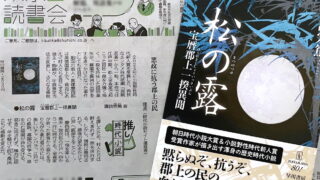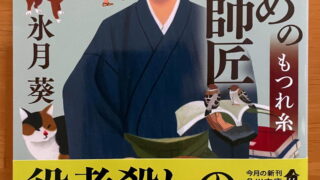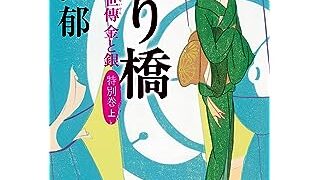(ひけんこらん)
(とべしんじゅうろう)
[剣豪]
★★★★
♪以前にこの本を買おうとして、間違った本を買ってしまったことがある。しかもその本は以前に購入していた本と同じ本だった。我ながらショックだった。それはともかく、1~2年ぐらい前の本を入手するのは、結構難しい。
戸部新十郎さんは、2003年8月13日に、77歳で死去された。ちょうどこの本は、その死の直前に文庫として刊行された。 戸部さんというと、剣術の流派とその真髄をエピソードで綴る「秘剣」シリーズが好きだ。端整な筆致のなかに、平明なことばと印象的な話で、剣の奥義を解き明かす、チャンバラファンならずとも面白く読める。本書にも9篇の剣術話が収録されている。
「六華」はしんとう流の有馬亀兵衛と居合術の村崎甚助が登場。「風水」は新陰流の疋田文五郎の弟子・島千四郎、「山影」は夕雲流の入江武左衛門といった、初めて聞くような兵法者を取り上げられている。「ほう捨」では、時代がぐっと下がって幕末の心形刀流の伊庭秀俊と八郎が描かれていて興味深い。
しかし、この本のキモは、作者の出身地である加賀国の剣術話のオンパレードである。古伝中条流の印牧弥二郎(かねまきやじろう)の子孫・明千坊と伊東弥五郎(一刀斎)の関わり合いを描く「茶巾」、富田流(とだりゅう)の富田越後守重政・富田一放の活躍ぶりを描く「夢枕」と「面影」。加賀の陰流の遣い手・天野覚右衛門が登場する「虎切」、富田流の六兵衛・小六の親子が振う秘剣「虎乱」など。
「虎切」と「虎乱」と似たタイトルが並ぶが、虎は身を翻して尾を持って敵を摶つということから、ともに脇構えの隠剣の一種。
「秘剣」シリーズは以下のとおり。
『秘剣水鏡』(徳間文庫)
『秘剣花車』(新潮文庫・徳間文庫)
『秘剣埋火』(徳間文庫)
『秘剣龍牙』(徳間文庫)
物語●「六華」大和多聞城の主・松永弾正のもとに、アルメイダというパードレがやってきて歓待された。弾正は、アルメイダに、召し抱えていた兵法者の有馬亀兵衛(ありまきへい)の六華と称する守備に徹する技と林崎甚助の抜刀術を見せた…。「茶巾」越中立山の山王坊に廻国修行者と思われる二人連れが、明千坊を訪ねてやって来た。明千坊は、立山に伝わる医薬を生業にする衆徒で、二人の兵法者のうち、主の方は病身で、明千坊の診療を願った…。「夢枕」前田利家の死後帰国した利長は、徳川家康から謀叛の疑いをかけられた。弁疏の使者として大坂城へ向かったのは、家老の横山大膳長知と兵法富田流宗家の富田重政だった…。「風水」落城目前の大坂城より、若衆髷の武芸者が柳生宗矩のもとに、新陰流開祖上泉伊勢守の高弟・疋田文五郎の使者としてやってきた。千姫を将軍家に戻すとともに、秀頼と淀の方の助命嘆願の申し入れだった…。「虎切」おやじ橋で、柳生宗矩の家来大坂九蔵が何者かに斬り殺された。柳生一門の長老が集まり、曲者が遣った太刀は、虎切と呼ばれるものだということがわかったが…。「面影」徳川・前田両家和親の証として、利常のもとに輿入れしてきた秀忠の二女・珠姫が産後の肥立ちが悪くて二十四歳の若さで没した。葬儀後、珠姫の侍女が江戸の公儀要路へ、利常の悪行を訴えた…。「虎乱」加賀藩の出頭人・大槻伝蔵が大坂出張の帰路で、二人の刺客に襲われた。家来の老士六兵衛の剣によって救われたが…。「山影」加賀浪人の倅・入江武左衛門は、夕雲流の小田切一雲の道場に入門し、剣を学んだ。一雲は名声が高く、道場は盛況を極めていたが、後継者問題で道場は乱れを生じていた…。「ほう捨」心形刀流伊庭八郎は、錦絵になるほどの美丈夫。講武所教授になった後、上洛する将軍家茂の奥詰に命じられたとき、二十一歳だった。上京前に、養父の八代目秀俊から“ほう捨”という秘剣を授けられた…。
目次■六華|茶巾|夢枕|風水|虎切|面影|虎乱|山影|ほう捨 ※「ほう」は金へんに立かんむりに方の字|解説 縄田一男