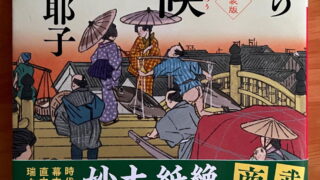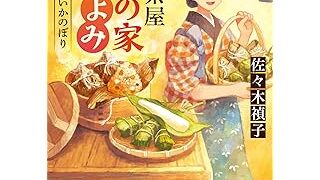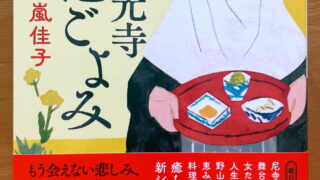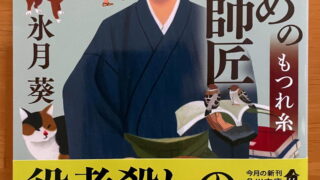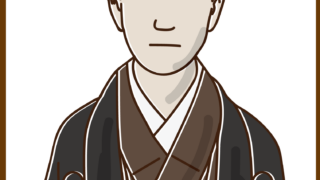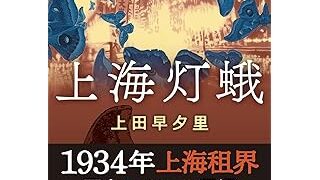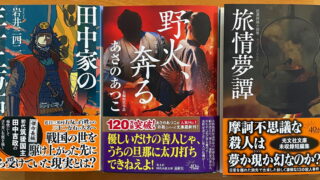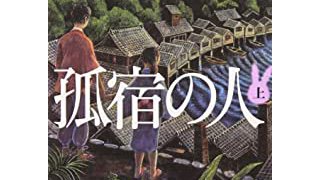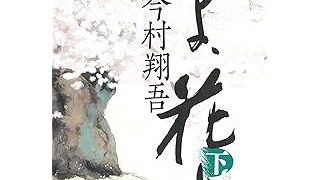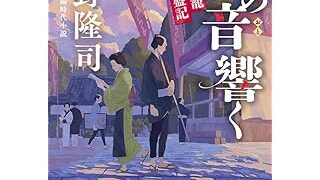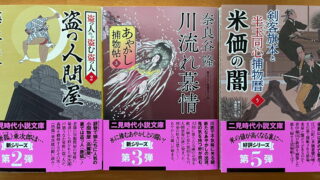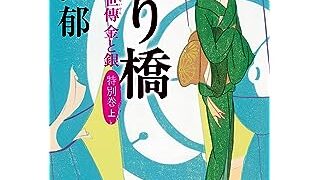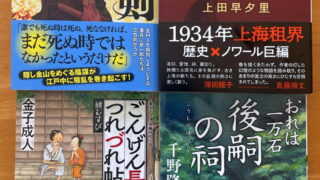(ひかれものでござい ほうらいやちょうがいひかえ)
(しみずたつお)
[街道もの]
★★★★☆
♪『つばくろ越え』に続く、「蓬莱屋帳外控」シリーズの第二弾。江戸・神田元岩井町にある飛脚問屋蓬莱屋の飛脚が主人公を務める連作形式の時代小説。本作は三話収録されているが、各話でそれぞれ異なる飛脚が主人公を務めるところがユニーク。飛脚といっても、江戸の町に書状を届ける町飛脚でも、江戸と京大坂を行き来する飛脚でもない。
治助が手代になった天保時代から世のなかの流れがものすごく速くなり、暮らしの仕組みが目まぐるしく変わりはじめた。
あたらしい商売がつぎつぎに生み出された時期でもあった。飛脚業の中身も変わらざるを得ず、甚兵衛は通し飛脚というあたらしい仕組みを考え出した。
早くいえば江戸から荷受け人のところまで、ひとりの飛脚が走りぬいて、荷をじかに送り届けるということだ。それによって、これまでかかっていた日数が半分以下になった。(『引かれ者でござい 蓬莱屋帳外控』P.267「観音街道」より)
このシリーズの面白さは、通し飛脚を主人公に据えたことである。そして、飛脚が荷を届ける先がいろいろな土地になる。本書でも、第一話「引かれ者でござい」は甲州であり、第二話の「旅は道連れ」では越後と会津の国境であり、第三話「観音街道」では上総が舞台になっている。道中や荷を届ける先の土地柄や暮らす人びとが描かれていて興趣が尽きない。
「なにをいただくんだ」
「金に決まってるだろうが。三百両。持ってきたんだろう?」
「たしかに持ってる。だがそいつは、おまえさんにやってくれといって預かってきたものじゃねえ」
「あたしの身代金だよ。だがそのあたしがやつらから無事逃げ出したってことは、やつらはもう受取人じゃないってこと。あたしの金」
「多賀屋惣右衛門さんの金だよ。たしかにおれはそれを運んできた。だがそいつは、おまえさんを助け出して、江戸へ連れ帰るという約束で預かってきたものだ。おまえさんに渡せとは、ひとことも言われてねえ」
(『引かれ者でござい 蓬莱屋帳外控』P.72「引かれ者でござい」より)
身代金を届けにきた飛脚鶴吉と、狂言誘拐を企てた商家のどら息子菊太郎の会話が面白い。通し飛脚は荷物ばかりでなく、ときには大金を運んだり、大切な人を送り届けたりする。そのため世間知と体力武力、度胸を兼ね備えていないと務まらない。まさにヒーローの条件だ。
「こんげに降り続いて、まーら降るろうか。天の底ぶち抜げたみてらなぁ」
訛りをまる出しにした嘆きの声が聞こえた。振り返ると、笈を背負った六十六部だった。(『引かれ者でござい 蓬莱屋帳外控』P.131「旅は道連れ」より)
「だすけ罰あたるもんが出て来ますて」
と言ったときの顔がなぜか口惜しそうだった。(『引かれ者でござい 蓬莱屋帳外控』P.142「旅は道連れ」より)
飛脚が行った先の雰囲気を伝えるために、効果的に方言を交えている。越後の方言の響きがなんとも懐かしい。
空が広くなっていた。
目の前が平らになっていた。
木という木がなぎ倒され、削り取られた赤い地肌が剥きだしになっていた。
なにもかもが倒れ伏している。横たわった大地。なにひとつ動かず、いまは静寂の刻を迎えていた。
山津波が起きたのだ。(『引かれ者でござい 蓬莱屋帳外控』P.184「旅は道連れ」より)
作品が発行されたのは2010年8月で、3.11の大震災前ではあるが、作品の舞台となった幕末も大地震が頻発していた。大雨、洪水、山津波、次々と天災に見舞われながらも、決死の山越えをする第2話のスリリングな展開に、かつての志水さんの冒険小説の名作を思い出して興奮した。
3話めでは、蓬莱屋の治助が店を辞めて故郷に帰り炭焼きになった後輩の次郎吉を訪ねる。久しぶりに再会した次郎吉は妻帯して娘をもち、一人前の男になっていた。仕事を一から教えて、厳しく育てた治助にとって、その姿は目を瞠るものがあった。そして、次郎吉らの炭焼きは上総に領地をもつ、ある藩の身勝手な施策に縛られていた…。
困難な立場に身を置きながらも、知恵と度胸で乗り越えようとする次郎吉の矜持。そして、その姿に共感して協力しようとする治助。男の友情が心地よい。シミタツ節が炸裂する一編。
プロとして、黙々と仕事をこなしていく蓬莱屋の面々のハードボイルドぶりが、たまらなく魅力的なこのシリーズ。次回作の『待ち伏せ街道』も早く読みたい。
主な登場人物◆
鶴吉:蓬莱屋の飛脚
勝五郎:蓬莱屋の帳外の仕事の元締め
仙造:蓬莱屋の飛脚
宇三郎:蓬莱屋の飛脚
治助:蓬莱屋の飛脚
甚兵衛:蓬莱屋の先々代
大賀甚内:甲州別所の私塾・萱ノ舎の師匠
菊太郎:越前堀多賀屋の若旦那
多賀屋惣右衛門:菊太郎の父
河津又之助:浪人。尊王玄武党の総裁
新堂英膳:浪人。河津の仲間
伝吉:遊び人
孫作:十九歳。百姓で駄賃稼ぎに荷運びをする
おけい:孫作の妹
喜十:元船頭の老人
米八:六十六部
喜之助:旅商人
粂蔵:やくざ
軍治:中間
銀三:人足風の男
仙石寺の住職
寿平:仙石寺近くの百姓の男
五平:木樵
いせ:武家の娘
大橋右之助:若党
宗吉:旅籠越後屋の主
幸作:炭焼きの男
太作:幸作の息子
おかじ:宇三郎の女房
ちよ:おかじの娘
熊之助:炭焼きの黒子
おふく:熊之助の女房
仙太郎:おふくの子ども
次郎吉:元蓬莱屋の手代で、今は炭焼き
はな:次郎吉の女房
こいと:次郎吉とはなの娘
元吉:炭焼きの爺さん
東作:炭焼きの男
作造:石工の手伝いの男
丈吉:和田屋の手代
豊八:炭焼き
伊作:炭焼き
おちか:伊作の娘
和:炭焼きの若い男
春吉:炭焼き
川畑の富太郎:炭焼き
八十吉:炭焼き
物語●
「引かれ者でござい」鶴吉は、憂国の志士をかたる無頼漢七人に、身柄を拘束された江戸の富商のどら息子菊太郎を救出するために身代金三百両を携えて甲州別所にやってきた。無頼漢どもは村の小さな寺子屋に巣食っていた…。
「旅は道連れ」出羽鶴岡からの帰りの宇三郎は、越後津川で大雨に見舞われた。阿賀野川の氾濫を恐れて、上流で川を渡る会津街道を選んだが、そこでも川止めに遭う。さらに上流を目指した宇三郎は、五人の男たちと道連れになってしまう…。
「観音街道」治助は、かつて同じ蓬莱屋で働き、弟のように育てた次郎吉を迎えに上総を訪れた。次郎吉は五年前に故郷に帰り久留里で炭焼きをしている…。
目次■引かれ者でござい|旅は道連れ|観音街道|解説 香山二三郎