(きみょうなしかく・ぎおんしゃ・しんとうじけんぼ)
(さわだふじこ)
[捕物]
★★★☆☆
♪澤田さんの新シリーズは、馬庭念流の達人で祇園社の神灯目付役・植松頼助(うえまつよりすけ)が主人公の連作捕物。神灯目付役とは、祇園社の境内各社の灯籠などに点された火の管理と、社の警護役がその職務で、神さまのお使いと見なされていて、京の人たちからは敬せられていた。その服装は、ねずみ色の筒袖に伊賀袴、腰に大小を帯び、足許は草鞋ばきで、黒い塗り笠に面垂れのいでたちだった。塗り笠には、「祇園社神灯目付役」の文字が、赤漆でくっきりと書かれていた。
植松頼助は、公家の庶子として生まれながら、訳あって今は、祇園社山門の東側に構えられる寄人長屋に盲目の浪人・村国惣十郎と暮らしていた。物語には、祇園社南楼門の茶屋・中村屋(楼)の娘・うず女(め)が彩りを添える。
澤田作品らしく、京の風物や当時の文化的な背景がきっちりと説明されていて、いろいろと勉強になることが多い。「おけらの火」ではおけら詣り、「奇妙な刺客」では祇園祭りの、当時の様子を詳細に描写して興味深かった。また、「花籠の絵」では、円山応挙が登場してびっくり。
物語●「八坂の狐」頼助は、見回り中に薬師堂の前で、一匹の白狐を見かけた。つかまえてみると、狐のお面をつけた十歳ぐらいの子どもで、母親に言われて賽銭泥棒に来ていたのだった…。「おけらの火」頼助は、本殿で参拝を済ませた二人の人物にあった。一人は、中村屋重郎兵衛で、もうひとりは中村屋に出入りの炭屋の手代だった。手代は、律儀そうな男で来年早々には暖簾分けしてもらうのだという…。「花籠の絵」頼助は、同役の孫市のなじみの料理茶屋で、襖絵を描いていた円山応挙と知り合った…。「奇妙な刺客」祇園祭り(宵山は別名〈屏風まつり〉とも呼ばれていた)が近づくなか、市中では、屏風に描かれた絵が奇妙に消えていくという噂が広がっていた…。
目次■八坂の狐|おけらの火|花籠の絵|奇妙な刺客|あとがき
時代:安永元年(1772)
場所:祇園社、団栗辻子、四条河原町、四条木屋町、末吉町、仏光寺、大雲院ほか
(廣済堂出版・1,600円・00/04/15第1刷・277P)
購入日:00/03/29
読破日:00/07/22


















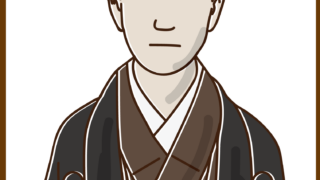

 [文庫あり=中公文庫]
[文庫あり=中公文庫]