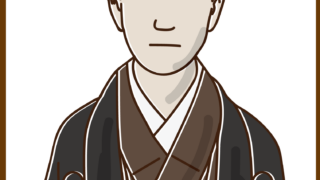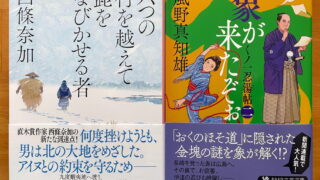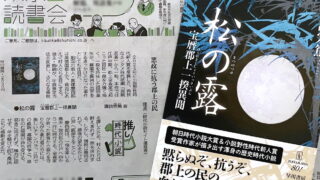(きっかしょう)
(はむろりん)
[武家]
★★★★☆☆
♪本書に登場する、筑前黒田藩藩士の立花重根(たちばなしげもと)と立花峯均(たちばなみねひら)の兄弟は、実在の人物。二人は、立花宗茂の家老職を務めて主家の姓を許された立花(薦野)三河守増時の曾孫にあたる。
兄の重根は、茶人として立花実山の道号を持ち、元禄三年に、千利休およびその高弟南坊宗啓の茶道の秘書といわれる「南方録」を書写して発表したことでも知られる。弟の峯均は、重根から茶道の薫陶を受けた高弟の一人であるばかりでなく、宮本武蔵の流れを汲む筑前二天流第五代の兵法家でもある。
筑前黒田藩というと、伊達騒動、加賀騒動と並ぶ三大御家騒動に数えられる黒田騒動でも知られる。本書は、黒田騒動が決着した後の時代が舞台になっているが、物語には、黒田騒動後の爪痕やしこりが残る中で実際に起こった御家騒動が描かれている。
「きょうから、ここがそなたの屋敷だ。わしを父と思って暮らすがよい」
ほっとして、思わず涙が出そうになったが、
「泣くでない。泣かなければ明日は良い日が来るのだ」
重根の静かな声に泣かずにすんだ。式台の重根の足下に桜の花びらが二、三、散っていた。重根は気づいて一枚を取ると、卯乃に手渡した。
(『橘花抄』P.8より)
物語の冒頭で、主人公の卯乃が重根の屋敷に引き取られて、初めて二人が出会うシーン。重根の所作と心持ちの美しさが伝わってくる。
香には〈六国五味〉という分け方がある、とりくは話した。
六国とは香木の産地のことで、
伽羅
羅国
真南蛮
真那賀
佐曾羅
寸聞多羅
である。香木は日本では産しないためいずれも海を渡って来たものだ。真那賀はマラッカ、寸聞多羅はスマトラ、羅国はシャムのことである。
五味は、甘、辛、酸、苦、鹹の五行に基づく区別である。甘は蜜を練る甘さ、辛は丁子の辛味、酸は梅のすっぱさ、苦は漢方薬の黄柏の苦さ、鹹は汗の塩辛さとされる。
聞香はこれらの香りを聞きわける遊びだが、さらに香を組み合わせることによって、源氏物語などの世界を表す楽しみがあるのだという。
「わたしは、茶は現世を味わい、香は古の物語を聞くものだと思っております。香木は遠い国からもたらされたもので、その香りは数百年の時を蘇らせます」(『橘花抄』P.35より)
卯乃は父の死に、重根が関与したと聞かされて、懊悩のあまり心が鬱して目が見えなくなってしまう。失明した卯乃に、重根の継母のりくは香道の手ほどきをする。
峯均と卯乃は座して釜の湯がしだいに沸く音を聞いた。
釜の湯音については、魚眼、蚯音、岸波、遠波、松風、無音などと表され、これを〈釜の六音〉という。釜が沸くにつれ、魚の目ほどの泡が立つ状態から地中で響くようなかすかな音がし始め、やがて岸辺や沖の波、松の梢を過ぎる松籟に聞こえてくるのである。
(『橘花抄』P.87より)
本書では、重根が茶書「南方録」をまとめた茶人ということもあり、茶を立てるシーンが意味をもった形で物語に挿入されている。
春の野にあさる雉の妻恋ひにおのがあたりを人に知れつつ
『万葉集』にある大伴家持の和歌だった。雉は春の野で妻を恋うて鳴き、自らの居場所をひとに知られるという。
「雉は妻恋鳥ともいうそうです」
「峯均様は、今もさえ様を恋うておられると言われるのですか」
「それはわかりません。ただ、もしそうだとすると、峯均殿は危うい目にあうのではないか、と思うのです」
りくは心配げに言った。
(妻恋鳥――)
卯乃の胸にりくの言った言葉がせつなく残った。(『橘花抄』P.105より)
峯均は、ゆえあって、さえと夫婦別れをしていた。(妻恋鳥――)、確かにせつなくなる言葉だ。
杉江は澄んだ空を見上げて言った。
「ひとは会うべきひとには、会えるものだと思っております。たとえ、ともに歩むことができずとも、巡り合えただけで仕合せなのではないでしょうか」
重根は、不意に胸の奥に痛みを感じた。
杉江の人となりを自分もまた愛おしんでいたことに気づいたのである。(『橘花抄』P.218より)
重根がなぜ卯乃を後添えに迎えたいと考えたのか、その理由の一つが、卯乃の母杉江への思いがあったのかもしれない。
「兄が血で認めた思いとは、かくのごとく赤心に発したものでございます。御家のためとあらば、諌めるのが臣下たる者の道でございましょう。されど、それがおのれの身をかばうためであってはなりませぬ。たとえ御意にかなわぬことでありましょうとも、言上せねばならぬと意を決した以上、どのような処罰でも甘んじて受けるのが武士の道と心得ます。兄はこれまで、家臣としてなすべきことをなして参りました。そのうえで鯰田村へ配流されました。決して後悔はいたしておらぬと存じます」
「座敷牢に入れられても悔いてはおらぬと申すのか」
「兄は、事に当たって悔いぬのが武士と心得ておりましょう」
(『橘花抄』P.318より)
武家小説の読みどころのひとつに、主人公の出処進退ぶりが武士の道に則っているかどうかということがあげられる。主人公が苛酷な境遇に置かれながら、時には懊悩したり憤怒したりしながらも、矜持を失わず精一杯生き抜いているからであり、そこから清冽感がにじみ出ているのだろう。
若いころ天馬に敗北し、その屈辱から一念発起して剣を修行した峯均だが、剣の神髄は敵を作らず、争いを避けることにあると悟ったという。
ある時、作兵衛は強いとはどういうことか、と峯均に訊ねたことがある。
「それは負けぬということだ」
峯均は笑って答えた。
「必ず勝たねばならぬということでしょうか」
「いや、違う。負けぬというのは、おのれを見失わないことだ。勝ってもおのれを見失えば、それはおのれの心に負けたことになる。勝負を争う剣は空虚だ」
武士とは、
――破邪顕正
の剣を振るう者の謂だ。この世の不正を正し、正義を明らかにせねばならぬ。そう峯均は教えた。
「それゆえ、武士が刀を抜くのは一生に一度か二度でよいのだ。一閃、邪を斬れば、生涯の務めは果たせる」
(『橘花抄』P.451より)
本書は、黒田藩の御家騒動を描いた傑作武家小説であるが、峯均の視点からは、剣豪小説として読み解くこともできる。
かつて、小倉藩の使者津田天馬に御前試合で敗北した峯均。婿入りした家から離縁され、幼い娘を抱えながら、再婚せずに剣の修行者に変わった峯均ならではの言葉。物語の終盤での峯均と天馬の再戦ともいうべきチャンバラシーンが圧巻。天馬が遣う剣が佐々木小次郎で知られる巌流というのが面白い。
主な登場人物◆
卯乃:黒田藩百石取りの藩士村上庄兵衛の娘
立花五郎左衛門重根:黒田藩隠居付頭取
立花平左衛門重種:重根の父で、元家老
りく:重種の後妻で、重根の継母
立花専太夫峯均:重根の弟で、二天流の達人
奈津:峯均の娘
桐山作兵衛:峯均の押しかけ弟子
彦四郎:立花峯均家の家士
つね:立花峯均家の女中
弥蔵:立花峯均家の下男
津田天馬:元小倉藩藩士で、巌流の遣い手
さえ:峯均の元妻
花房七十郎:さえの弟
藤森清十郎:さえの再婚相手で、黒田藩世子吉之付きの小姓組三百石
隅田清左衛門:黒田藩家老
真鍋権十郎:隅田に仕える家臣で、村上庄兵衛の友
黒田光之:黒田藩三代藩主で、隠居
黒田綱政:黒田藩四代藩主
黒田泰雲:光之の嫡男で綱政の実兄
黒田吉之:綱政の嫡男で、世子
月瀬十郎兵衛:綱政の側近
杉江:卯乃の母
野村太郎左衛門:黒田家の六千五百石の重臣
村橋弥兵衛:野村太郎左衛門の家臣
笹倉庄右衛門:重根を監視する武士
佐野道伯:江戸の目医者”
物語●十四歳の春に、父親を失った卯乃は、筑前黒田藩の隠居付頭取を務める二千百五十石の身分の立花五郎左衛門重根(たちばなごろうざえもんしげもと)に引き取られた。そして、四年、十八歳になった卯乃に重根の後添えになる話があった。
その直後、卯乃は亡き父の旧友という真鍋権十郎から、父の自害に重根が関与していたという話を聞き、懊悩のあまり失明してしまう……。
失明した卯乃は、重根の弟・峯均(みねひら)の屋敷に移り、峯均やその娘奈津、重根の継母のりくらと暮らすことに。峯均は、重根より十六歳年下で、この年三十五歳。兵法狂いと呼ばれるほど剣術に熱心で、宮本武蔵が創始した二天流の相伝を受けていた……。
目次■第一章 卯花/第二章 姫百合/第三章 山桜/第四章 乱菊/第五章 花橘/解説 末國善己