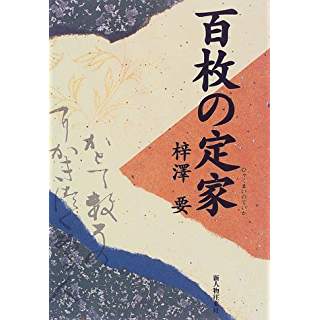
百枚の定家
(ひゃくまいのていか)
梓澤要
(あずさわかなめ)
[歴史ミステリー]
★★★★☆☆☆
♪この作品は、時代小説ではないが、時代小説好きを大いに満足させるミステリー小説。ミステリーの分野の一つに、歴史の謎をテーマにしたものがある。高橋克彦さんの『写楽殺人事件』(講談社文庫)や井沢元彦さんの『猿丸幻視行』(講談社文庫)、高木彬光さんの『成吉思汗の秘密』などがその成功例。事件の謎を解くとともに、歴史の謎にも挑戦するので、一粒で2倍も3倍も面白いのである。もっとも、下手な作者の手にかかると、中途半端に終ってしまうのだが…。
便宜上、今後、歴史の謎をテーマにした現代小説を「歴史ミステリー」、ミステリー性の高い時代小説(捕物とも、伝奇ものとも、政争ものとも言いきれない作品)を「時代ミステリー」と呼ぶことにする。(ときどき癖でミステリと「ー」なしで、表記してしまうことがあるのは、一頃、早川書房のミステリにはまっていた時期があったせいです)。
百人一首という高尚な遊びをしたことがなく、暗記している歌も2、3首という、まったくの門外漢ながら、この物語はわくわくしながら読めた。膨大な資料を駆使して、読者を定家の世界へと誘う作者の筆力に感動した。
小倉色紙は、百人一首を編纂した藤原定家が自ら一首ずつしたためた、小倉百人一首のオリジナルで、七十四歳の老齢で中風と眼疾に悩まされながらも書き上げたということです。定家の死後、忘れられいつしか行方不明になり、二百五十年後に連歌師宗祇の手で甦り、千利休の師・武野紹鴎らにより賞賛され、それを所持することがステイタスになっていった。信長が、光秀が、細川幽斎が、秀吉が、徳川家が、競って手に入れたという。小倉色紙は大名家や豪商の秘蔵の宝となり、明治・大正時代になると、没落大名家からいっせいに流れ出し、政治家・財界人に買い漁られ、その一方で贋作も次々に出たといういわくのある美術品だ。読後にわかに藤原定家の書への関心が高まり、どこか美術館へ行ってみたくなった。
物語●都心から1時間圏内の通勤圏にある埼玉県磯崎市(架空)に、新しく武蔵野美術館がオープンすることになった。学芸員の秋岡渉らは、そのオープニング展の準備に入っていた。そんな折、ニューヨークのオークションで、百人一首のオリジナルといわれる藤原定家の小倉色紙が出品され、高額で日本人の手によって落札されたというニュースが入ってきた…。失われた定家自筆の“小倉色紙”の謎に挑む異色歴史ミステリー。
目次■プロローグ/第一章 武蔵野美術館/第二章 小倉色紙/第三章 偽作と模作/第四章 海外流出/第五章 十枚の色紙/第六章 巨木斃れる/第七章 谷底の町/第八章 雨の刃/第九章 定家葛/第十章 謎の紙背文字/第十一章 贋作者の真実/第十二章 仕掛けられた罠/第十三章 定家になった男/エピローグ/小倉色紙一覧/あとがき

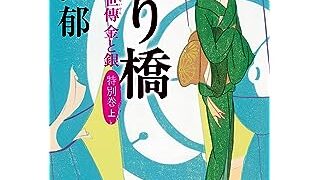
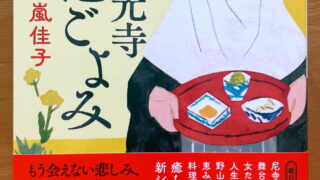
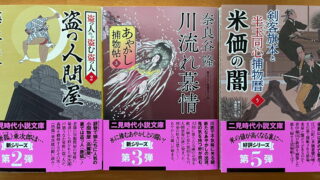

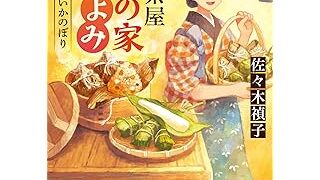
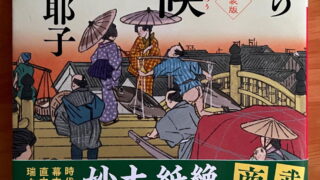


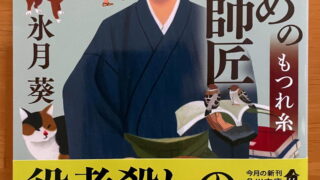
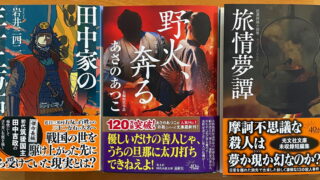

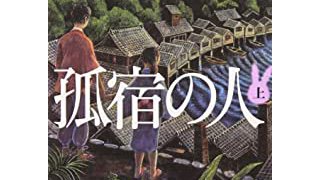
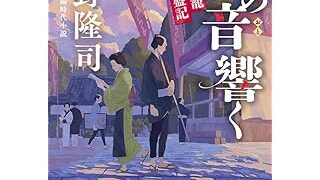

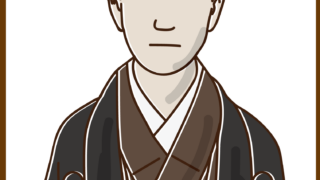
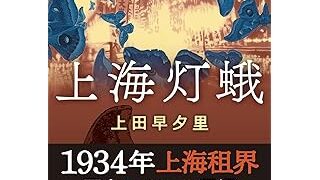
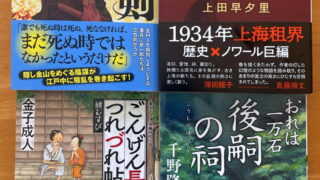
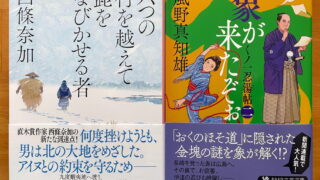
 [文庫あり=幻冬舎文庫]
[文庫あり=幻冬舎文庫]