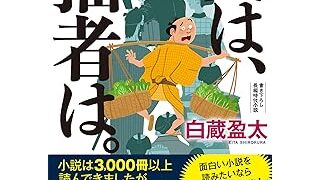『もゆる椿』|天羽恵|徳間書店
 天羽恵(あまうめぐみ)さんは、2022年に「日盛りの蝉」で第6回大藪春彦新人賞を受賞しました。
天羽恵(あまうめぐみ)さんは、2022年に「日盛りの蝉」で第6回大藪春彦新人賞を受賞しました。
受賞作「日盛りの蝉」は中編の時代小説です。
女郎のおさきは、ある日、楼主に呼ばれ、見知らぬ若き侍・藤岡と仮初めの夫婦を演じることを命じられます。藤岡は敵を討つため、おさきの力が必要だと……。
2023年、『もゆる椿』(徳間書店)で単行本デビューし、同書では、2024年の第13回日本歴史時代作家協会賞新人賞の候補に選ばれています。
道場剣一筋の真木誠二郎は、裏目付の佐野に見込まれてある御役目を言い渡される。尊王攘夷派の黒幕を誅殺すべく、江戸から京まで刺客の供をせよというのだ。
鬼のような刺客と聞いて生来の臆病者である誠二郎は怯えるが、現れたのは年端もいかない少女・美津だった――。(『もゆる椿』カバー帯の内容紹介より)
文久二年(1862)冬。
五百石の旗本の次男坊で二十歳の真木誠二郎(まきせいじろう)は、ふた月前に「裏目付として働かぬか」と目付衆の佐野から声をかけられました。
裏目付の主たる務めは、御小人のような間諜で、上様直々の命で動くこと。
誠二郎は小野派一刀流の目録は得ていて、部屋住みの身から脱する機会を喜ぶ半面、道場剣に加えて生来の臆病者で血腥いお役目が務まるのかという不安が身の内でせめぎあっていました。
佐野は、親兄弟にも役目のことは知られてはならないとして、誠二郎に家を出て町家に家移りするように命じ、支度金を与えました。
ひと月あまり過ぎたころ、佐野から、尊王攘夷の浪士を操る黒幕を誅殺するという密命を告げられ、誠二郎はその暗殺の実行役である刺客を連れて京へ向かえと命じられました。
「いかに御役目であっても、人の命を絶つというは、誰にでもできる所業ではない。それをたやすくこなせるのが、里の住人じゃ。皆が皆、人斬りに長けた者ども故、里の外へ出すは、鬼を巷に放つも同然。長旅となればなおさらじゃ」
佐野は言葉を切ると、勿体をつけるように身動ぎした。
「そこで道中、かの者が無体な真似をせぬよう、傍について手綱を握る者が必要となる」
「……その御役目を、私に?」
「さよう」(『もゆる椿』P.33より)
裏目付は、多摩の外れに隠れ里を設け、殺生を生業となす者たちを隠れ住まわせていると。ところが、指定された品川宿の旅籠で誠二郎の前に現れた刺客は……。
「お待たせさんどすえ」
おかしな挨拶をしながらオンんが入ってきた。いや、女と呼ぶには語弊がある。まだ稚児髷が似合いそうな子どもだ。
「何も頼んでおらぬぞ」
抜けかけた腰をかばうように姿勢を戻しながら、誠二郎は娘と向き直った。(『もゆる椿』P.41より)
誠二郎はその宿が抱える年少の飯盛女(女郎)と勘違いして帰そうとするが、見かけに似合わずその少女・お美津が刺客でした。
鬼のようないかつい体の浪人者を想像していた誠二郎にとって、大きなギャップ。
とても刺客には見えないお美津は十二歳でしたが、居合の達人の抜き打ちが止まって見えるほどの天賦の動体視力を持ち、加えて隠れ里で刺客の技を仕込まれ、これまで的を仕損じたことが一度もないと。
何事においても考えすぎて悲観的になってしまうがどこか抜けている誠二郎と、そんな誠二郎を亡き兄のように慕うがわがままで幼いお美津の二人の京までの東海道中でいろいろな出来事が起こり、その珍道中ぶりに面白くて引き込まれました。
お美津の辛い過去も明らかになっていき、ともすると悲しく重いテーマになりがちのところですが、お美津に対して恐れや嫌悪といった感情が湧いてこないのは、人の心を持つ鬼だからかもしれません。
兄妹のような二人の間に絆が育まれていくところが好ましく、ロマンチックなエンタメ時代小説として楽しめます。
もゆる椿
天羽恵
徳間書店
2023年10月31日初刷
装画:洵
装幀:大武尚貴
目次
なし
本文280ページ
書き下ろし
■今回取り上げた本