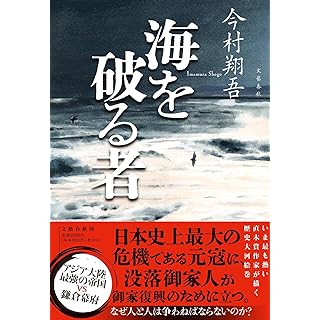『海を破る者』|今村翔吾|文藝春秋
 今村翔吾さんの『海を破る者』(文藝春秋)は、元寇をテーマにした歴史小説です。
今村翔吾さんの『海を破る者』(文藝春秋)は、元寇をテーマにした歴史小説です。
地理的に恵まれている島国ということもあって、日本はこれまで外国から侵攻された経験がほとんどありません。
そんな中で日本史上最大の危機は、その相手や規模からいって、鎌倉時代中期に2度にわたり、当時アジア大陸最強のモンゴル帝国の元によるに日本侵攻、いわゆる元寇(文永の役と弘安の役)です。
しかしながら、元寇について、日本史の教科書の簡単な記述程度しか知識がなく、本書の主人公である、伊予国の御家人・河野六郎通有(こうのろくろうみちあり)についても、本書に出合うまで全く知りませんでした。
かつては源頼朝から「源、北条に次ぐ」と言われた伊予の名門・河野家。しかし、一族の内紛により、いまは見る影もなく没落していた。一族はお互いに疑心暗鬼に陥っていた。現在の当主・河野通有も惣領の地位を巡り、伯父と一触即発の状態にあった。
しかしそんな折、海の向こうから元が侵攻してくるという知らせがもたらされる。いまは一族が骨肉の争いに明け暮れている場合ではない。通有は、ばらばらになった河野家をまとめあげ、元を迎え撃つべく九州に向かうが……。(『海を破る者』(文藝春秋)カバー帯の紹介文より)
源頼朝より、「源、北条に次ぐのは河野よ」と称えられたほどの武家の名門、伊予河野家でしたが、六郎の曽祖父通信が承久の乱の折、京方に加担して惨敗したため、所領のほとんどを幕府に没収されていました。
領地を大幅に減らしながらも命脈を保った祖父の通久には、通時、通継の二人の子がありました。元来なら兄の通時が河野家を継ぎ、弟通継は分家させるところ、文永四年(1267)、祖父は突然通時を義絶して、通継を当主にすると宣言しました。兄の通時は通久の愛妾と通じたと。今から十一年前、六郎が齢十八のことでした。
伯父は密通していたのは弟通継のほうだと反論しますが、祖父は取り合わず、父とともに兵を起こし、攻め立てるという暴挙に出ました。翌年に祖父は病で亡くなりますが、父と伯父の戦いは続き、家中を二分する骨肉の争いの中で、父は伯父に討たれてしまいます。
父を目の前で討たれながらも、当主となった六郎は、伯父との和解の道を探ります。
弘安元年(1278年)の晩夏、大きな船が停泊する浜・水居津(みいつ)。
「妖らしいぞ」「いや、天女様が降りてこられたらしい」と、人買い(奴隷商人)に連れられた金色の髪に碧色の眼をした娘を見た、市に集まった人たちが騒いでいました。
六郎は金髪碧眼の娘を一目見ると、息を呑んで立ち尽くし、やがて買い取ろうと言いました。
「勘違いするな」
六郎が女を欲したのは肉欲を満たす為ではない。牛馬のように何かの役に立てようとするのとも違う。また華美な調度品を買って愛でたいという欲求とも異なった。
――この女の話を聞いてみたい。
という至極単純な思考である。海の向こうに何があるか、この女ならば知っているのではないかと直感したのかもしれない。
(『海を破る者』 P.39より)
六郎の考えは周囲の者たちに誤解され、同じ人買いのもとにいた高麗人らしい男からも、「銭で女を買い、己の意のままにしようとしている」と恥知らずと責められました。
六郎は、その高麗人にも興味を持って引き取り、金髪碧眼の娘に令那、高麗人の男に繁と名前を与え、令那には家事全般を仕込むように命じ、繁には自ら漁を教えることにしました。それは下僕として酷使する意味合いではなく、生きていくために何かしらの仕事をしなければならないと考えたからです。
二日後、六郎は、領内の外れの一の滝で、大伯父通広の子、通秀と密かに会いました。通秀は六郎と同じように、まだ見ぬ地に激しい興味を抱き、また、戦うことの愚かさを訴え続けていて、妙に馬が合っていました。通秀は、相克の争いに陥った河野家を出て出家して、今は一遍という僧侶になっていました。
六郎は一遍を通じて幕府の動向に関する情報を得て、世の動きに目を配り処世をしなければと思っています。目下の懸念は、元が日ノ本を諦めてはおらず来襲する機をうかがっていること。
「元は何のために戦っているのだろうな」
二人は問答を通して、いくさを止める手掛かりをつかもうとします。
繁と令那の河野家での暮らしに慣れたころ、六郎は二人の国の話を聞きました。
家族を皆元に殺されたという繁。
ずっとずっと西にある「るうし」という国の「きいえふ」という町にの生まれたという令那。今のウクライナあたりでしょうか?
「西にないと申しました。この世の何処にでも哀しみはあります……しかし見えにくいだけで、この世の何処にでも幸せもあるものと思います」
耳を傾ける一遍に向け、六郎は静かに、それでいて凛然と言い切った。
「人と人が向き合う間に、私が見た夢の国はあります」
「良かった」
一遍が口を綻ばせる意味が解らず、六郎は首を捻った。
「それは?」
「儂にそれを教えてくれたお主が折れては困る」
(『海を破る者』 P.258より)
六郎と一年ぶりに再会した一遍は、この一年踊念仏に力を入れていました。が、一方で、あるかも説けぬ楽土を説くだけで人の心を真に安んじることができるのか、死後のことばかりを考えさせるのは生を享けたことへの冒涜ではないか、この世にいながらにして楽土を感じさせる術はないのか、と思い悩んでいました。
一遍は、踊念仏を編み出す気付きをくれた六郎が、その答えにたどり着いたことがうれしかったのです。
「ほんの些細なことでも、相手に通じることを見つけられた時、共に手を取り合うことも出来る」(P.259)という言葉が胸に強く残りました。
ウクライナでロシア軍の侵攻が、中東ガザで戦争が、行われている今、戦いが身近になっているにもかかわらず、はるか遠くの国のことのように無関心だったり、願望からくる根拠の薄い楽観主義だったりでは、東国の鎌倉武士たちと同じかもしれません。
平素からなぜ戦わなければならないのかを自問し、理解し合えることはないのかを懸命に探ることが大切なことを改めて気づかせてくれます。
物語は、言葉が通じなくても、考え方が違うことを受け入れて、相手を理解しようと懸命につとめる主人公・河野六郎通有が、2回目の元寇に立ち向かっていく姿を描いていきます。
いくつかの事件や出来事を通して、バラバラだった家中の意思を一つにまとめ、やがて元に立ち向かう姿には深い感動を覚えます。
肥後の御家人で『蒙古襲来絵詞』で知られる、猛者の竹崎季長(たけざきすえなが)の登場や、「河野の後築地(うしろついじ)」と御家人たちに呼ばれた勇猛な陣立てなど、元寇での戦いの場面も圧巻です。
手に汗握る海戦もあって、海洋小説ファンとしても大満足で、後半からはページを繰る手も加速がついて終章へ。
主人公の戦いぶりも含めて、その生き様を刮目したい、と思いページを閉じました。
戦争が世界のどこかで起きている時代。
だからこそ、今、読みたい歴史小説です。
海を破る者
今村翔吾
文藝春秋
2024年5月30日第1刷発行
装画:荻原美里
装幀:征矢武
目次
第一章 邂逅の夏
第二章 眩惑の秋
第三章 決心の冬
第四章 真実の春
第五章 西海に至る
第六章 河野の後築地
第七章 海を破る者
終章
本文459ページ
初出
別冊文藝春秋 2020年3月号~2024年1月号
■今回取り上げた本