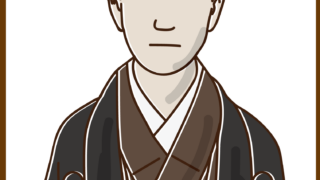『桎梏の雪』|仲村燈|講談社
 仲村燈(なかむらとう)さんの長編時代小説、『桎梏の雪』(講談社)を紹介します。
仲村燈(なかむらとう)さんの長編時代小説、『桎梏の雪』(講談社)を紹介します。
著者は、2021年、本作で第15回小説現代長編新人賞奨励賞を受賞しデビューを果たした期待の新鋭です。
タイトルの「桎梏(しっこく)」とは、辞書によると手かせ足かせの意味で、人の行動を厳しく制限して自由を束縛すること、またはそのもの。
江戸時代後期の将棋界で、しのぎを削る若き棋士たちの対局と青春を描いた、本格将棋時代小説です。
文化六年(1809年)、江戸将棋界の重鎮・九世名人大橋宗英が惜しまれつつ世を去る。しかし、将棋三家、大橋家・伊藤家・大橋家の分家(宗与家)の間での名人後継ぎ選定は家元間の政争激しく、伊藤家の宗看が十世名人を襲名するまでには16年もの歳月を要してしまう。大橋分家七代目当主・宗与は、その間に生じた将棋家の衰退を憂いていた。自身は父宗英から棋才を継ぐことができなかったものの、鬼才・英俊を養子に迎え将棋家再興のため尽力する。養子ゆえの気後れを見せつつも、英俊は名人宗看に次ぐ実力者へと成長していった。妹で初段棋士の弦女も宗与家に活気を与える存在であった。まだ幼い宗与の嫡子・鐐英も、大橋家の弟子・留次郎(後の天野宗歩)と友情を分かち合いながら日々研鑽を積んでいく。しかし、それとは裏腹に本家と分家の間には確執が生じていた……
(『桎梏の雪』Amazonの紹介文より)
江戸の将棋所は、大橋本家、大橋分家(宗与家)、伊藤家が公儀より権を預かる家元三家から成ります。
不世出の棋士、九世名人大橋宗英が死没し、以来十六年間、名人が空位となり、将棋所は衰微していました。
大橋本家当主の十一代宗金はまだ若く、本家の重責を担うにはまだ力不足でした。
大橋分家の当主七代目宗与は、宗英の嫡子で、将棋家立てなおしにかける想いは強いが、棋力は平凡。後継者の英俊やまだ幼い実子の鐐英に期待をかけています。
伊藤家では、昨年、長男の看理を亡くし、後継ぎには、次男の看佐が繰り上がっていました。棋才にかけては兄をも凌ぐ麒麟児ながら、身持ちが悪く、放蕩の癖がおさまりません。このごろは宗与家の後継ぎである英俊まで悪所に連れまわしています。
「伊藤家、宗与家の後継ぎが揃って放蕩とあっては、いよいよ宗金殿が頼りです。まだ宗桂を名乗るつもりになれませぬか」
「ええ、宗桂を名乗るのは七段目に上がってからと決めております。宗桂の名をことさらに重んじるのは、父と同じく家格を驕っているよう聞こえるかもしれませんが」
「お父上のこと、あまり悪く申しまするな。養子ゆえ、気負うところもあったのでしょう」
「しかし将棋家の落ち目は父の愚かゆえです。鬼宗殿はよくぞ耐えておられます。さぞや……」
(『桎梏の雪』 P.14より)
文政八年(1825)、当代一の棋力を持つ鬼宗こと、伊藤家の宗看が十世名人に就きました。
宗与の養子英俊は若手筆頭の実力を持ちながらも、気弱な気質から大一番では冴えず不覚を取ることも。
それに引きかえ、英俊の妹のお弦は、外向けには初段格と言いながらも、宗与をして「あれが男であったならどれだけ良かったか」と嘆かせる棋才を擁していました。
将棋経験のある著者ならではの、棋士たちのリアルな心情描写が魅力的で、駒の基本的な動きがわかるくらいで、将棋に疎い読者の私も、随所に織り込まれる臨場感豊かな対局場面に引き込まれていきました。
物語は、家元三家の当主と次代を担う後継者たちを中心に展開していきます。
とくに、英俊とお弦、看佐の三人の若者が将棋に懸ける青春群像は読みごたえ十分です。
さらに、宗与の幼い嫡子、鐐英と大橋本家の内弟子、天野留次郎の幼い二人の存在も、将棋所の復興に一役買っています。
碁・将棋家を管轄する寺社奉行土井利位の用人として、蘭学者としても知られる鷹見十郎左衛門が登場するのも見逃せないところです。
桎梏の雪
仲村燈
講談社
2021年7月26日第1刷発行
装画:卯月みゆき
装幀:芦澤泰偉
●目次
第一章
第二章
第三章
第四章
第五章
第六章
本文267ページ
■Amazon.co.jp
『桎梏の雪』(仲村燈・講談社)