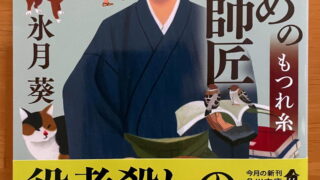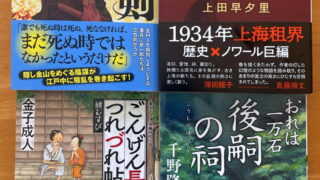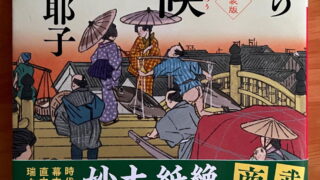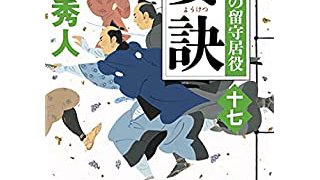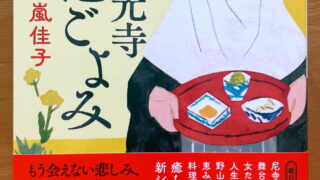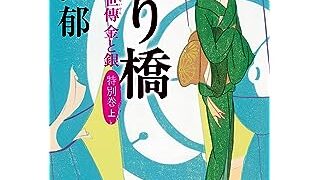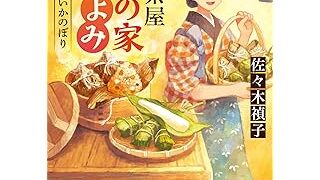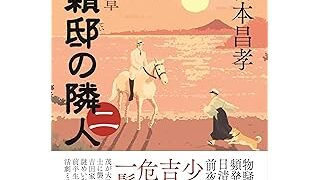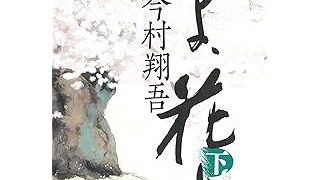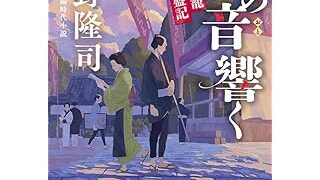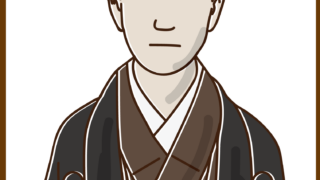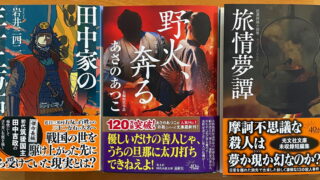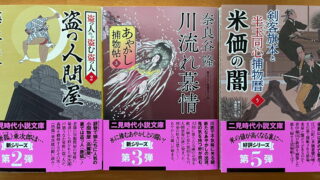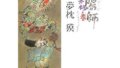日本橋三越で開催されていた「第2回 江戸老舗 味と技の大江戸展」に行ってきた。江戸から続く名店の味と職人の技に出合える貴重な催しで、ここ数年毎年楽しみにしている。最終日の午後ということもあったのか、大勢の来場者で盛況だった。
豊島屋本店のブースで新発売の「無濾過純米原酒 十右衛門」を早速試した。すっきりした飲み口でいろいろな料理に合いそうなおいしいお酒だった。十右衛門とは、名物の白酒を売り出した初代豊島屋十右衛門の名にちなんだものだそうだ。会場内で作っているところを見ていてあまりにおいしそうで、羽二重団子と梅園の桜餅を買って帰る。
豊島屋の開業は、江戸慶長年間。徳川家康が江戸に入り、江戸城の大改修が行なわれた時期だという。
さて、遅ればせながら、NHK大河ドラマの原作『功名が辻』全4巻を読み終えた。『功名が辻』の主人公山内一豊が亡くなったのは慶長十年(1605)九月。千代は十二年後の元和三年十二月に亡くなった。
『功名が辻』の巻末で、作家の永井路子さんが司馬さんの小説を以下のように解説している。
平安期の女流作家の紫式部と清少納言の作品を比較してよく言われることに、紫式部のは「あはれ」、清少納言のは「をかし」の文学だという批評がある。が、この問題は、単に平安女流のことだけに終らず、その後も日本の文学の流れの中に、姿を変え、形を変えながらもずっと続いているのではないだろうか。そして、司馬さんの小説は、いわばこの「をかし」の系譜を引き継いだものではないか、と私は思う。
『功名が辻』を読みながら感じていた違和感というか引っかかりが氷解した。ドラマの影響や他の歴史小説との比較から、どうしても人間の葛藤や歴史のダイナミズムというものを歴史小説に期待してしまう。しかし、この作品にはそういった常套手段で感動を与える部分は少ない。歴史のターニングポイントである関ヶ原の戦いについても、一豊が後衛警備の隊に回されたこともあり、戦闘シーンがほとんどないままに終わっている。
司馬さんの意図として、われわれに主人公への共感を持たせて感動させるというよりも、土佐二十四万石を勝ち取ったこんな面白い女がいるということを知らしめることに、重きを置いているように思われる。ついでに、その手の上で踊らされた一豊とはこんな男だったんだよ、と教えてくれる。
土佐国入り後の二人の会話が何とも象徴的だ。
「おれが馬鹿で無能だからか」
「早く申しますと、左様なことになります」
(第四巻 P.296)
「をかし」の文学を究めた、司馬さんの小説の凄味を感じた瞬間でもある。

- 作者: 司馬遼太郎
- 出版社/メーカー: 文藝春秋
- 発売日: 2005/03/10
- メディア: 文庫
- クリック: 8回
- この商品を含むブログ (56件) を見る