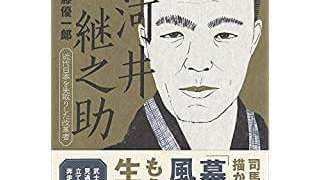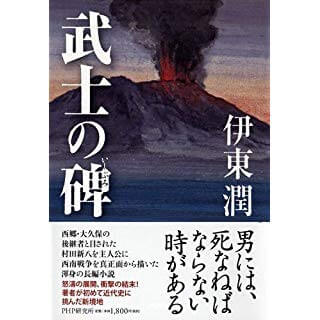伊東潤さんの『武士の碑(いしぶみ)』(PHP研究所)を読みました。西郷隆盛・大久保利通の後継者と目され、薩摩、そして日本の将来を託された男・村田新八を主人公に、西南戦争を真正面から描いた長編小説です。
伊東潤さんの『武士の碑(いしぶみ)』(PHP研究所)を読みました。西郷隆盛・大久保利通の後継者と目され、薩摩、そして日本の将来を託された男・村田新八を主人公に、西南戦争を真正面から描いた長編小説です。
本書は、戦国時代小説で活躍している伊東さんの初の明治小説です。取り上げたテーマが西南戦争ということで、刻々と記されていく男たちの葛藤、臨場感あふれる戦闘シーンなど、戦国小説に相通じるところがあり、作者の並外れた筆力が堪能できます。
西郷隆盛が下野したとの報に接した村田新八は、留学先のフランスから帰国。大久保利通と西郷の“喧嘩”を仲裁するために、故郷鹿児島へ向かった。しかし、大久保の挑発に乗った桐野利秋ら鹿児島士族が暴発して薩軍を挙兵する。新八もそれに否応なく巻き込まれていく。ここに、日本最後の内戦・西南戦争が始まった……。
西郷が下野した時、桐野や篠原は内心、「こいで、おいたちの西郷先生を取り戻せる」と思ったに違いない。新八には、その心情が手に取るように分かる。
「新八さん、おいたちは先生を、日本の西郷先生ではなく薩摩の西郷さん、つまい、おいたちだけの西郷さんにしておきたいちゅう気持ちが、あっとじゃなかか」
物語では、薩摩人にとって西郷隆盛とはどういう存在なのか、なにゆえ西南戦争が起こったのかを明らかにしていきます。また、桐野利秋は、池波正太郎さんの『人斬り半次郎』で馴染みはありましたが、村田新八の事績についても無知でした。
「日本に関心がおありですか」
「はい。色彩豊かな国と聞いています」
先ほどまでの疲れ果てた顔が嘘のように、ラシェルの顔が少女のように輝いた。
フランス人が、浮世絵を通じて日本に強い関心を持っていることを、新八は思い出した。
海外派遣先のパリで、新八は、病気で患っている若い女性ラシェルと浮浪児マランと出会う。ラシェルは、画家ギュスターヴ・クールベの私生児ながら、娼婦をしていて病を得たという。かれらはパリで生活する者の最下層に属し、半ば廃屋と化した建物の屋根裏部屋で暮らしていました。
西南戦争の戦いの日々の中に、パリでの生活の回想シーンが挿入されます。新八が薩摩の“木強者(ぼっけもの)”として生きて死んでいくだけの存在から、楽器コンサーティーナ(手風琴)を戦場に持ち込む、血の通った魅力的な人間として浮かび上がってきます。
「ああ、約束する。われらは戦い続ける。そうすることで、政府のやり方に物言える民が一人でも増えれば、われらの戦いはむだではなかったことになる。そのために――」
新八の声音が強くなる。
「われらは、最後の一兵まで戦い抜く」
本書を読むまで、西南戦争がどういう戦争だったのかをほとんど教えられてこなかったことに気付かされました。負け戦という悲劇的で血腥いものを扱いながらも、読後の余韻は良かったです。この戦いがわが国最後の内戦になったからかもしれません。
■Amazon.co.jp
『武士の碑』
『武士の碑』(PHP文芸文庫)
『人斬り半次郎 賊将編』(池波正太郎・新潮文庫)