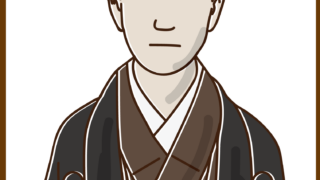嶋津義忠さんの『幸村』(PHP研究所・PHP文芸文庫)は、2016年NHK大河ドラマ「真田丸」の主人公・真田幸村の大坂の陣でのを戦いぶりを描いた歴史長編です。
嶋津義忠さんの『幸村』(PHP研究所・PHP文芸文庫)は、2016年NHK大河ドラマ「真田丸」の主人公・真田幸村の大坂の陣でのを戦いぶりを描いた歴史長編です。
関ヶ原の戦い後十一年にわたり、紀州九度山に閉居させられた真田昌幸・幸村の父子。昌幸を病で亡くし、幸村は弔いを済ませると、家康を倒して、徳川の世に大きな風穴を開けるために起ちあがった。
幸村は、来るべき戦いに向け、長宗我部盛親、後藤又兵衛、塙団右衛門、明石全登らの牢人を大坂方に引き入れる。さらに、稀代の忍者猿飛佐助、真田忍びを束ねる霧隠才蔵らに加えて、関ヶ原で死んだはずの島左近も味方に従え、“最後の戦い”大坂の陣の幕が上がる……。
戦国時代の掉尾に一瞬のきらめきを示して、後世に大きな名を残した幸村。その活躍ぶりは、これまで多くの小説に描かれてきています。本書では、慶長十六年(九度山で父・昌幸が労咳で亡くなるところから物語が始まります。
それにしても、この男を動かしているのは、一体、なにか。忠でも孝でも、大義でもない。名か。それも違う。
しかし、目の前の幸村は己を信じて揺るぎがない。向かい合っていると、その柔らかい外貌に似合わぬ、激しく凄まじい力を感じさせられる。
幸村の顔に穏やかな笑いが浮かび上がる。
「おれは家康が生きている限り、あの皺首を狙い続ける。佐助、間違えるなよ。おれは死ぬことなど、一度も考えたことはない。人は死と正面から向き合う必要はないのだ。放っておいても、死という奴は、背後から不意に襲って来る。これを防ぐことは、なかなかに難しい。だから、知らぬ顔をしておればよいのだ」
「名」、「義」や「忠」といった他の武士たちとは違う価値観で動く、幸村の「戦びと」ぶりが強烈に伝わってきます。また、猿飛の剣の遣い手で稀代の忍びながら、人を殺したことがない猿飛佐助のキャラクター設定もユニークで、物語の興趣を高めています。忍びといえども、武将の道具ではなく血の通った人として描く、作者らしいところ。
昌幸の命名になる流星の陣形とは、魚鱗の陣形よりもっと細く鋭い隊形を意味する。迅速な移動と、槍を突き出すごとく敵陣深く突入できる機能を有している。野戦において大軍を相手にしたとき、これを突き破って敵本陣に迫り、敵の大将首を挙げることを目的にした必殺の陣形である。
読み進めていくうちに、“最後の戦い”に向けて、徳川方と豊臣方の緊張が高まっていく感じが何ともスリリング。そしてその戦いでは、昌幸と幸村の二人で細部まで練り上げた“流星の陣”で家康を追い詰めます。戦国時代小説の面白さがギュッと詰まっています。
■Amazon.co.jp
『幸村』