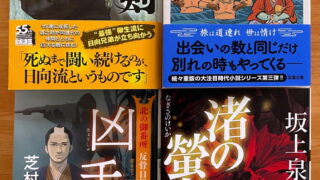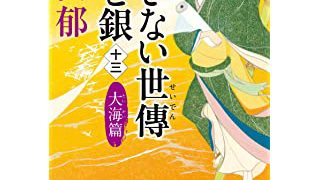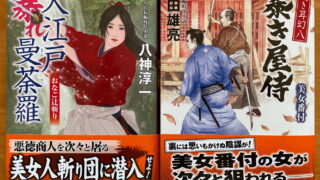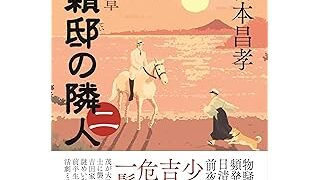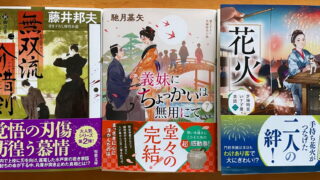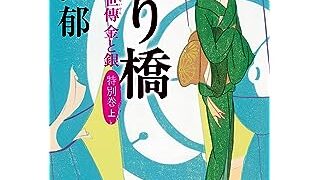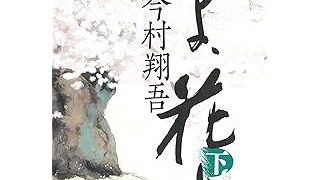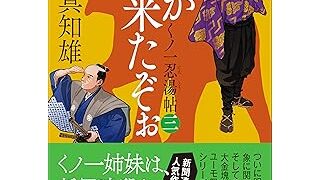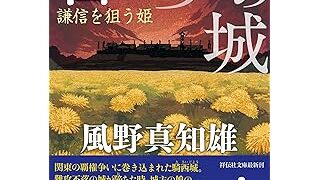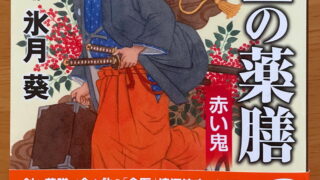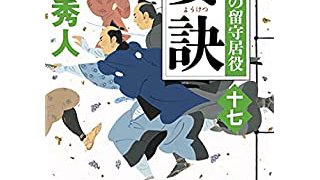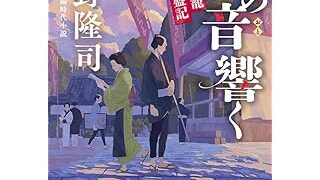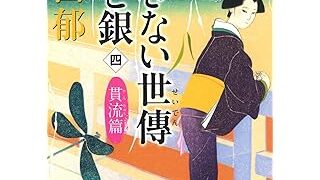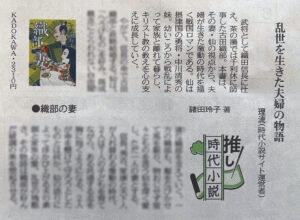 2025年4月19日(土)の東京新聞(中日新聞では4月20日)の朝刊・読書面「推し時代小説」のコーナーにて、本の紹介をさせていただきました。
2025年4月19日(土)の東京新聞(中日新聞では4月20日)の朝刊・読書面「推し時代小説」のコーナーにて、本の紹介をさせていただきました。
「推し時代小説」は、書評家の細谷正充さん、文芸ジャーナリストの内藤麻里子さん、文芸評論家の木村行伸さんと私が週替わりで、おすすめの歴史時代小説を取り上げる連載企画です。
今回、私がご紹介したのは、諸田玲子(もろた・れいこ)さんによる歴史時代小説
『織部の妻』(KADOKAWA)です。
作品について
『織部の妻』は、戦国武将であり茶人としても知られる古田織部(古田重然)と、その妻・仙の波瀾に満ちた生涯を描いた歴史小説です。
古田織部といえば、NHKでアニメ化もされた山田芳裕さんの漫画『へうげもの』の主人公として広く知られています。
そのため、織部自身が「へうげもの」(=ひょうきんな者)と呼ばれていたのだと、私自身、誤解していました。
「へうげもの」という言葉が史料として確認できるのは、茶人・神谷宗湛の日記、慶長四年二月二十八日付の記述とされています。
一ウス茶ノ時ハ セト茶碗 ヒツミ候也 ヘウケモノ也
このように、当初は「人(者)」ではなく「茶碗(物)」に対して用いられていたことが分かります。
本作『織部の妻』の中でも、以下のようにその言葉が登場します。
――そういえば。あなたは〈へうげもの〉がお好きでしたね。
(おう、さようさよう。大ぶりの、少しいびつで、こう、ほっくりと手になじむ……)
(『織部の妻』P.10より)
型にはまらない闊達さと、優れた美意識を備えた古田織部。
織田信長、豊臣秀吉、徳川家康と天下人が移り変わる中、武人として、そして茶人として仕えた織部の真の姿が、妻・仙の視点から描かれています。
歴史の陰に埋もれがちな女性の存在を通じて、織部の魅力を新たに照らし出す戦国小説です。
今回取り上げた本
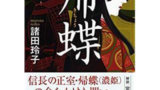
東京新聞「推し時代小説」バックナンバー