 戦後七十年。終戦の日に合わせて、植松三十里(うえまつみどり)さんの『調印の階段 不屈の外交・重光葵』(PHP研究所・PHP文芸文庫)を読みました。
戦後七十年。終戦の日に合わせて、植松三十里(うえまつみどり)さんの『調印の階段 不屈の外交・重光葵』(PHP研究所・PHP文芸文庫)を読みました。
この作品は、単行本刊行時に読んでいて再読になります。(その時の読書録はこちら)
1931年4月29日、駐華公使の重光葵(しげみつまもる)は天長節と上海事変の戦勝祝賀式典の会場で爆弾テロに遭い、右脚を失う。厳しいリハビリを、家族の支えで乗り越えて、外交の第一線に復帰し、孤立する日本を救うために日中戦争を終結させようと奔走するが、戦局は拡大の一途をたどる……。
敗戦直後、再び外務大臣になると、誰もがためらう降伏文書への調印を引き受け、連合国最高司令長官マッカーサーとの交渉に挑むのだった……。
物語の序盤で、爆弾テロに遭いながら、死線を越えてベッドに横たわる重光が、
「朝鮮にも、いい人は大勢いる。それどころか、いい人の方が、ずっとずっと多い。だから篤は、敵など討たなくていいんだ」と、まだ幼い息子・篤を諭すシーン。大隈重信が外務大臣のときに爆弾を投げつけられた際の逸話がもとで、重光が心から大隈を尊敬し、外交官を志したことも紹介されています。そして、
「片脚を失う苦痛は、僕などは計り知れないものだろう。でも君は片脚の代わりに、得がたいものを身につけた」
見舞いに訪れた、元外交官で代議士の松岡洋右(後の外務大臣)は、「義足で歩けるようになって外交の場に復帰してくれ、と励ますシーンで、胸が熱くなり落涙しました。
戦争を起こさないための楯になり、それでも起きてしまった場合は、早期終結に努める。それこそが自分に課せられた役目だと、明確に意識し始めていた。
第二次世界大戦の開戦前、駐イギリス日本大使に就いた重光は、アメリカの参戦前に日中戦争を終結させることを目指して、チャーチルと交渉して日英宥和を計ろうとします。
「四海とは、まさに日本の周囲だ。もちろんヨーロッパもアメリカもだが、近隣の国々への配慮も大事だ。それを志にせよ。自分が東洋人であることも、忘れてはならぬ」
江戸時代まで、日本は中国から文化を取り入れ続けてきて、韓国もあこがれの国として交流していたが、明治維新後三、四十年で国力が逆転して近隣の国々を見下すようになったことを漢学者だった父に指摘されます。重光は、外交官になりたての頃に父からおくられた忠告の辞「志四海」を胸に、日本が東洋と西洋の架け橋にならんと外交に命を賭けていく姿が感動的です。
終戦後、重光は戦犯として拘置されて、東京裁判で有罪に処せられます。同じく戦犯となった元軍人たちがこぞって裁判では自分は和平を望んでいたと主張します。そんな中で、元首相でA級戦犯の東條英機から、「私が憎まれて死んで、陛下に罪が及ばぬのなら、それで本望だ。ただ、誰にも止められなかった。あの怒濤の中で、陛下は和平を望んでおいでだった」ことを伝えてほしいと託されます。
「きっとボタンの掛け違えは、松岡さんよりも、もっと前から始まってたんですよ。日清日露の戦争の頃から。ひとつ戦争に勝つたびに、日本人は自信を深めて、勘違いを重ねてきた。自分たちは、どんな戦争にも負けないと」
獄中で、重光は敗戦に至るまでの経緯を綴り始めます。
歴史は勝者によって語られる。子供たちにも勝者の正義が教え込まれる。敗者の言葉になど、誰も耳を傾けず、敗者の書いたものなど、ただの言い訳だと思われて、誰も読まない。
それでも重光は信じた。書き残しておけば、いつか誰かの目に触れると。いつか誰かが理解してくれると。
今回、再読してみて、初読時に読み飛ばしてしまった大切なことに気付かされました。重光が、戦争の時代に外交官として国の命令に従いながらも、人の命の重さを知り、与えられた条件の下で可能な限り平和を希求していく姿が感動的。終戦七十年、今こそ読んでおきたい一冊です。
■Amazon.co.jp
『調印の階段 不屈の外交・重光葵』









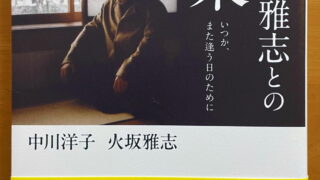










コメント