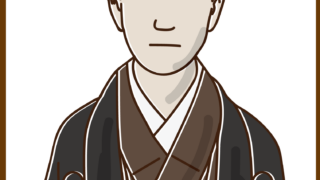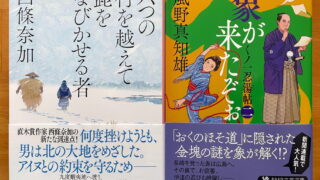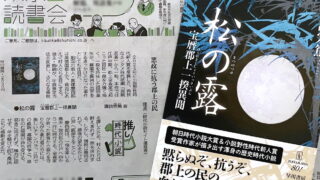「愛し合ってるかい?」の言葉をいつも投げかけていた、ロッカーの忌野清志郎さんは亡くなってしまった。訃報に触れて、かつて何度も聞いた歌が流れ、生前の映像が流されると、切なくなってしまう。合掌。
清志郎さんのおかげかどうかはともかく、今、日本には「愛」という言葉は、ごく普通の当たり前の言葉として使われている。そして、ほとんどの小説は「愛」をテーマにしているといっても過言ではないくらい。
「愛」という言葉とは逆に忘れられようとしている言葉がある。「義」という言葉だ。Yahoo!の辞書「大辞泉」では、儒教における五常の一。人として守るべき正しい道。道義。「仁・―・礼・智・信」と書かれている。どういう意味なのかよくわからない。「大辞林」では、儒教における五常(仁・義・礼・智・信)の一。人のおこないが道徳・倫理にかなっていること、と書かれている。
時代小説家の池宮彰一郎さんは、「義」を「我」を「美」しくと説き、「義」をテーマに多くの名作を残された。
回りくどくなったが、北方謙三さんの『楊家将』に続き、その続編にあたる『血涙 新楊家将』を読んで、心に残った言葉が「義」であった。本当は、ゴールデンウィーク前に読んでしまったのだが、読了後すぐは、作品に圧倒されてしまい、「戦うことでしか生きられない男たちの壮烈なドラマに胸が震えるぐらい感動した」ぐらいしか、感想が思い浮かばなかったこともある。
『血涙 新楊家将』は、前作の終わりから2年が経過したところから物語は始まる。楊家軍は、味方である宋の将軍の裏切りで、家長の楊業とその息子たちの多くが戦死したり行方不明になったりし、壊滅的な打撃を受けた。かろうじて生還した楊六郎と七郎によって楊家軍再興への道が開かれるが、残った兵たちもわずかで、その前途は多難。

- 作者: 北方謙三
- 出版社/メーカー: PHP研究所
- 発売日: 2006/12/07
- メディア: 単行本
- クリック: 3回
- この商品を含むブログ (30件) を見る

- 作者: 北方謙三
- 出版社/メーカー: PHP研究所
- 発売日: 2006/12/07
- メディア: 単行本
- クリック: 2回
- この商品を含むブログ (24件) を見る
「楊六郎か。久しいのう。七郎も生きていると聞いたが」
「はい。私と七郎は、生き残っております」
「朕が、いや私がいま生きてあるのは、楊業をはじめとする、楊一族の働きに負うところが大きい。たった二人とはいえ、生き延びてくれたのは、嬉しいぞ」
「ありがたき、お言葉です」
こういう言葉をかけられても、心の底からありがたいとは、到底思えなかった。楊家は楊家で生きていく、と一昨年の戦以来、ずっと思い続けてきたのだ。
(『血涙』上巻P.32より)
一方の遼では、将軍耶律休哥(やりつきゅうか)のもとに、かつて宋の将軍ながら記憶を亡くして遼の将軍となる石幻果(せきげんか)が加わっていた。石幻果こそ、楊業の四男・四郎延朗だった…。
宋と遼の存亡を賭けた戦い。その中で繰り広げられる軍閥・楊一族の戦い。戦うことを宿命付けられた彼らを動かすものは、領土や金銭、名声、地位といった「欲」ではなく、実は「義」なのではないだろうか。それゆえに、読み進めるにしたがって共感し、感動が高まっていく。
「義」は滅びや死につながる悲劇性と背中合わせである。今、ブームの戦国武将たちも西軍側に人気が集まっているのも、彼らが「義」に殉じたとされるからであろう。
私が育った昭和の時代、子どもの名前に「義」(義男、義隆、和義…)をつけることも珍しくなく、「義」という言葉が重かったように思う。今に目を移すと、人々は自己「愛」ゆえに「モンスター」化し、それは社会の劣化につながっている思われてならない。この作品を映画化やゲームやマンガにしたら、若い人たちや女性にももっと「義」という言葉を身近に感じるようになるんじゃないかなあ。楊六郎の「吹毛剣」と石幻果の「吸葉剣」などはゲームにしたら、魅力的な武器になるんだが…。夜、ベッドで『楊家将』と『血涙』を映画化した場合のキャスティングを妄想しながら、そんなことも思ってみた。
おすすめ度:★★★★☆☆