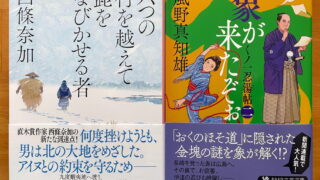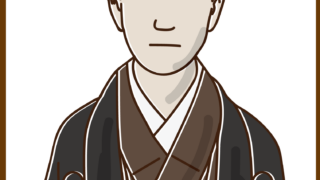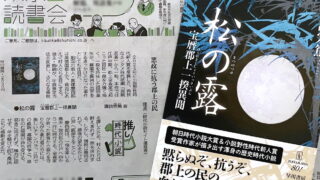山本兼一さんの『利休にたずねよ』(PHP研究所)を読んだ。作者の山本さんは、安土城を作った男を主人公にした『火天の城』で松本清張賞を受賞し、直木賞候補にも選出される、新作が最も注目される時代小説家の一人。戦国時代のテクノクラート(第一級の工人)を描いた傑作が多い作家だけに、利休をどのように描くのか、期待を込めて読み始めた。

- 作者: 山本兼一
- 出版社/メーカー: PHP研究所
- 発売日: 2008/10/25
- メディア: ハードカバー
- 購入: 4人 クリック: 25回
- この商品を含むブログ (93件) を見る
――わが一生は……。
ただ一碗の茶を、清寂のうちに喫することだけにこころを砕いてきた。この天地に生きてあることの至福が、一服の茶で味わえるようにと工夫をかさねてきた。
――わしが額ずくのは、ただ美しいものだけだ。
(『利休にたずねよ』P.10)
自身の絶対的な美学をもって、天下人の秀吉と対峙し栄耀を極めた、死を賜った利休。
「あなた様には、ずっと想い女がございましたね」
利休の死を目前にし、妻・宗恩は、利休の心の奥底に住み続ける女の存在への嫉妬を口にする。
懐から袋を取り出した。美しい韓紅花に染めた麻の上布だが、すっかり色褪せてしまった。
なかに小さな壺が入っている。
掌にすっぽりおさまる緑釉の平たい壺で、胴がやや上目に張っている。香合につかっているが、すがたは瀟洒で、口が小さい。もとは釈迦の骨をいれた舎利器だったかもしれない。
全体にまんべんなくかかった緑釉に、深みと鮮やかさがある。
多くの名物を手にした利休が、肌身離さずにもつ、緑釉の香合の由来とは…。物語は、天正十九年二月二十八日の朝、利休が切腹の朝から始まる。時系列の逆にさかのぼる形で利休の恋、死を賜ることになる理由、そして、彼を形成する美意識の謎を、秀吉や家康、信長、石田三成ら、周囲の人物の視点を交えて解き明かしていく。
読んでいくうちに、利休の美―彼の用いる名物と対峙するような緊張感と高揚感に包まれ、一気に読むのがもったいないような気分になった。一つ一つが計算され、余分なものや無駄なところがない、端正な文章が美しく、期待を裏切らない傑作である。