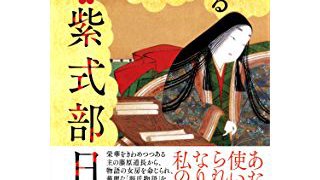和田はつ子さんの『手鞠花おゆう』を読み始めた。江戸の若き歯科医、藤屋桂助が活躍する「口中医桂助事件帖」シリーズの第2作目。
口中医桂助の周囲で事件が発生し、その解決に桂助と相棒で房楊枝職人の鋼次、医師の娘志保が活躍するという、捕物スタイルの連作時代小説である。物語の背景に、江戸時代の歯医者事情が描かれていて興味深い。医者が活躍する時代小説はいくつかあるが、歯医者というのは新鮮。
たとえば、歯周病は江戸時代、歯草(はくさ)と呼ばれていた。また、お歯黒の風習についても解説されていた。
当時、女たちは結婚すると、お歯黒といって、必ず歯を黒く染めるならわしがあった。黒は他の色に染まらないことから、“貞女二夫にまみえず”という貞節の象徴であった。かねわかし、かね水入れ、お歯黒壺などのお歯黒道具は、大切な婚礼道具であった。
また、酢酸第一鉄のかね水を、はじめて新婦が歯につける儀式には、かね親が欠かせなかった。かね親は、新婦側の親類縁者の中から福徳の備わった女性何人かが引き受けたものだった。かね親たちは、かねわかしでこしらえた自家製の“かね”を持ち寄って混ぜ合わせ、それで新婦にかねつけの初体験をさせたのである。
『手鞠花おゆう』P.25より
時代小説を読んでいると、虫歯に悩む主人公はほとんど出てこない。まして、口中医にかかりつけの登場人物もいない。実際のところ、江戸の人はやはり虫歯は少なかったのだろうか。お菓子やケーキなどの甘い物が少なく、砂糖が貴重品だった時代だから、虫歯にもなりにくかったのかな。そうすると、富裕な商人や高貴な人たちの間では、歯の病気で悩む人も少なくなかったかも。うーん、気になる。

- 作者: 和田はつ子
- 出版社/メーカー: 小学館
- 発売日: 2006/02/07
- メディア: 文庫
- この商品を含むブログ (7件) を見る